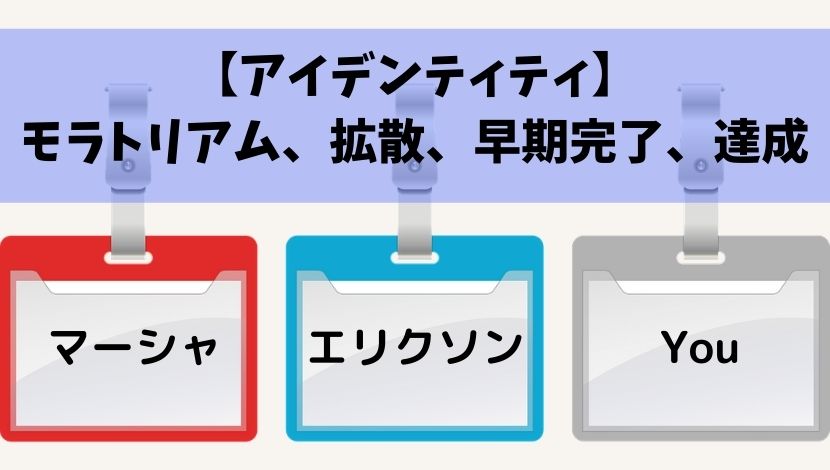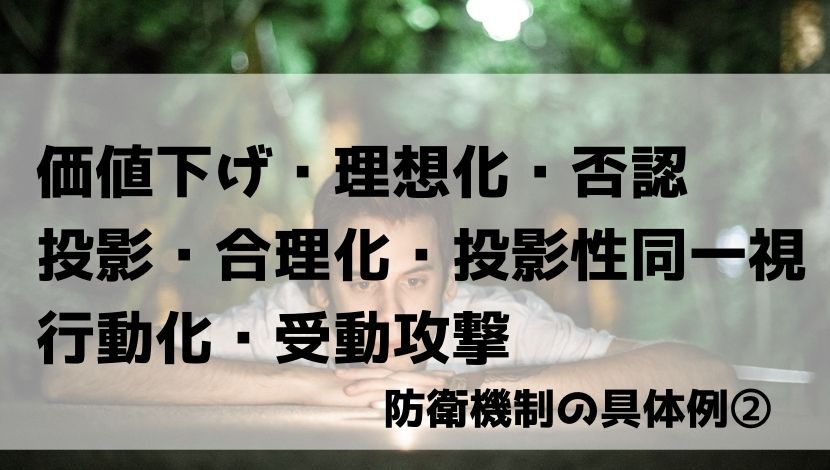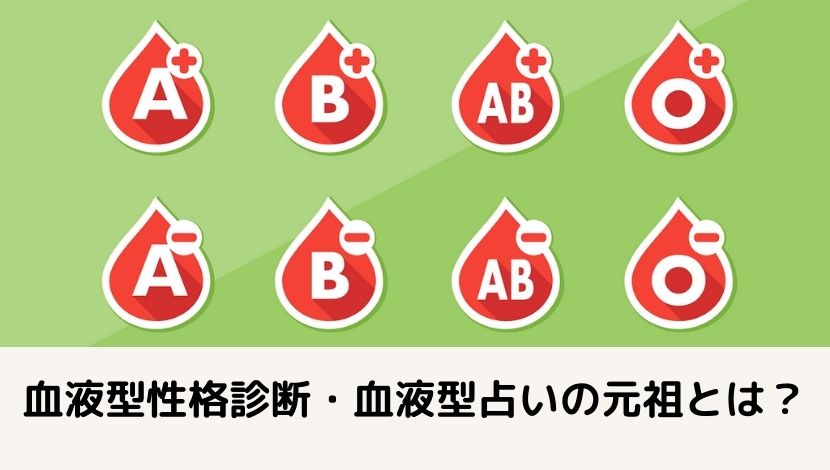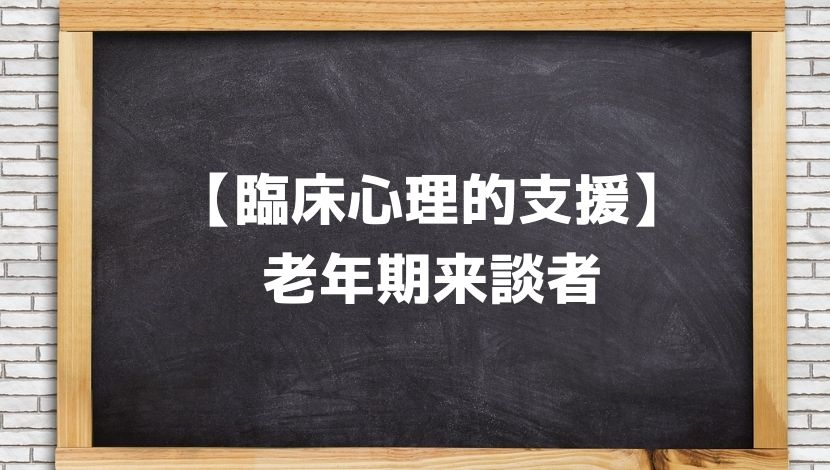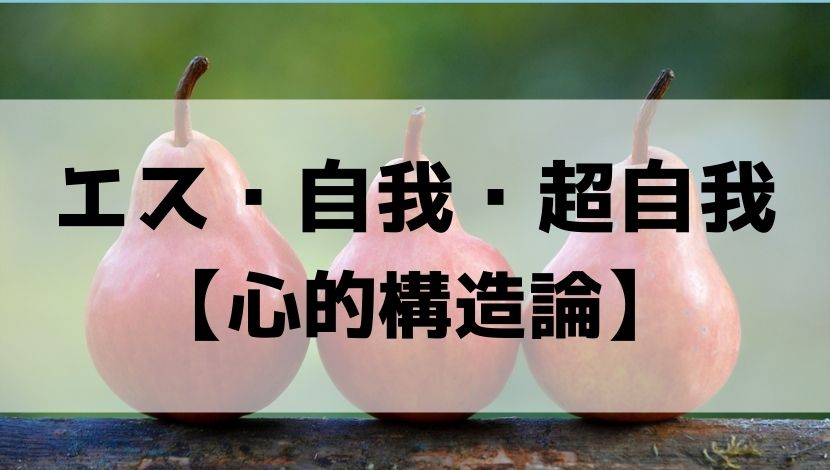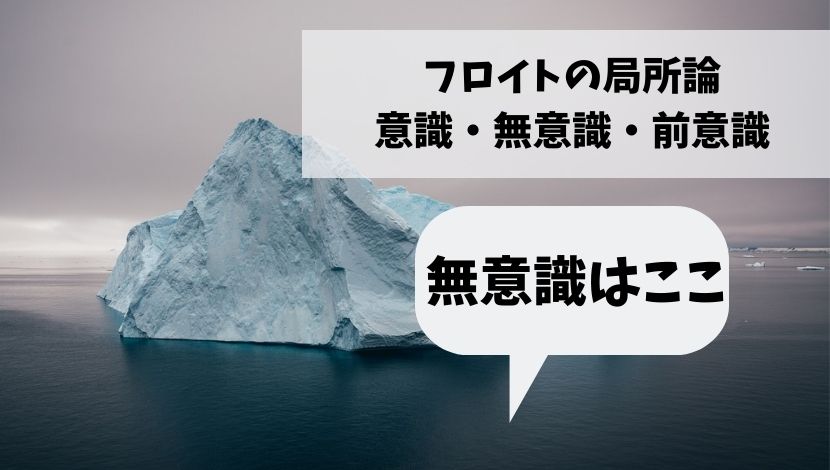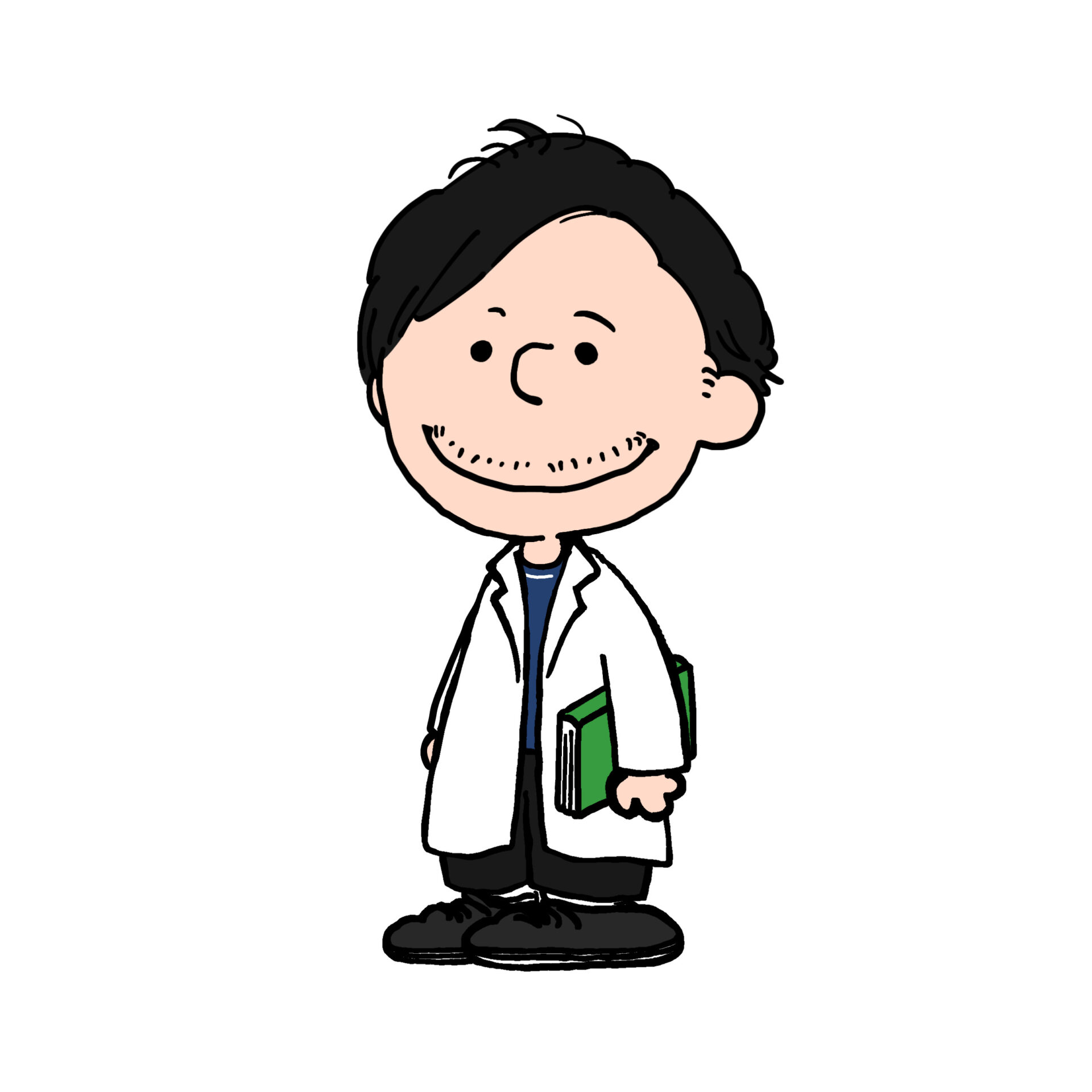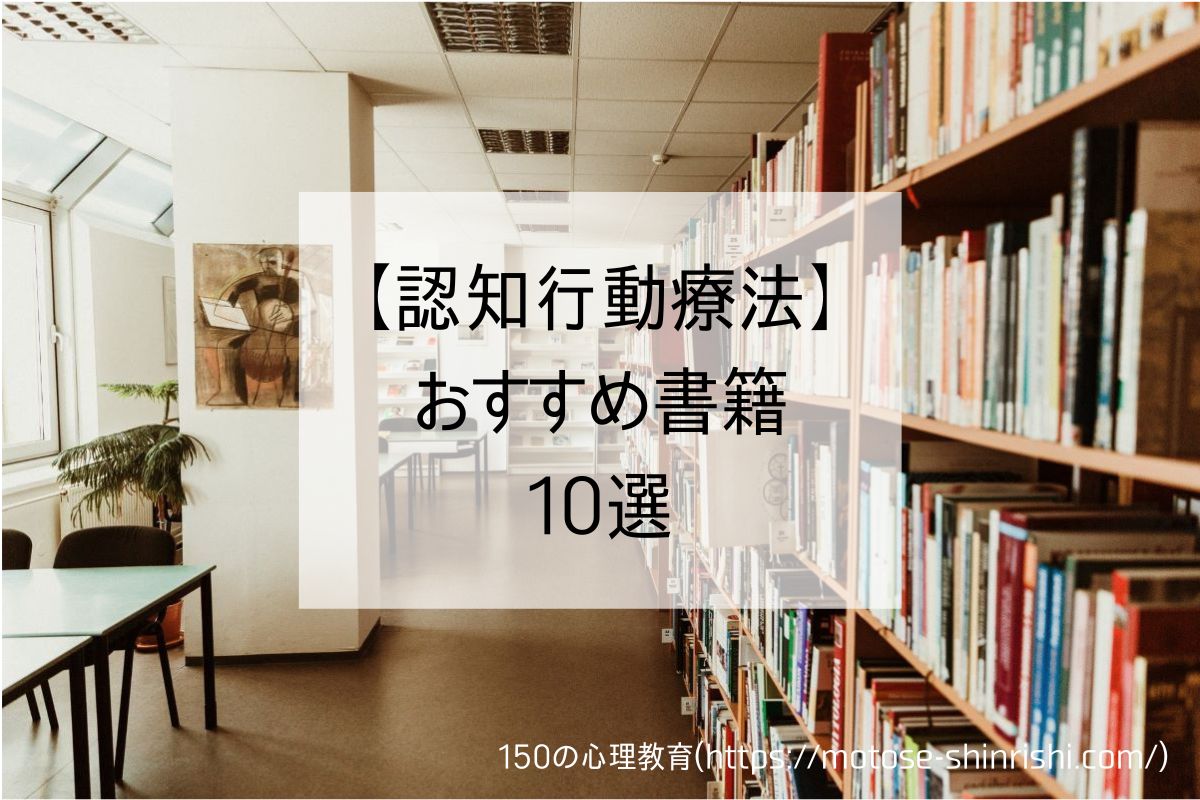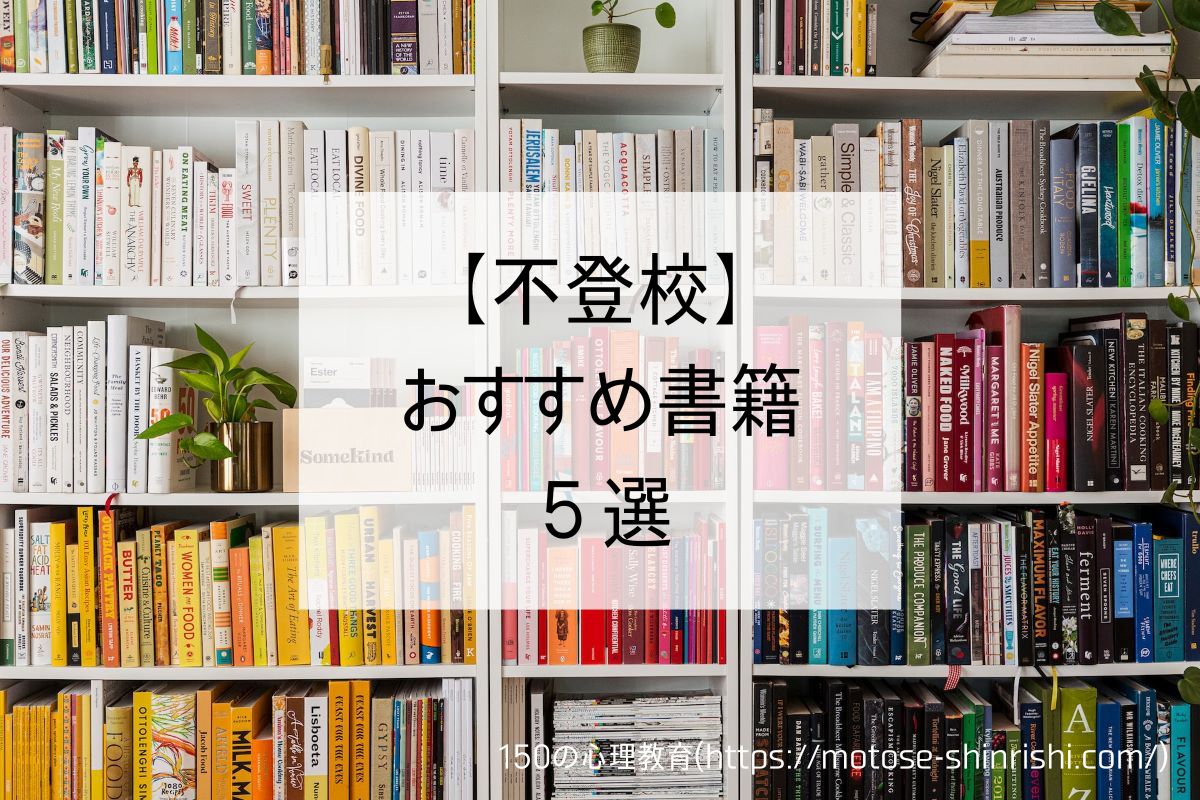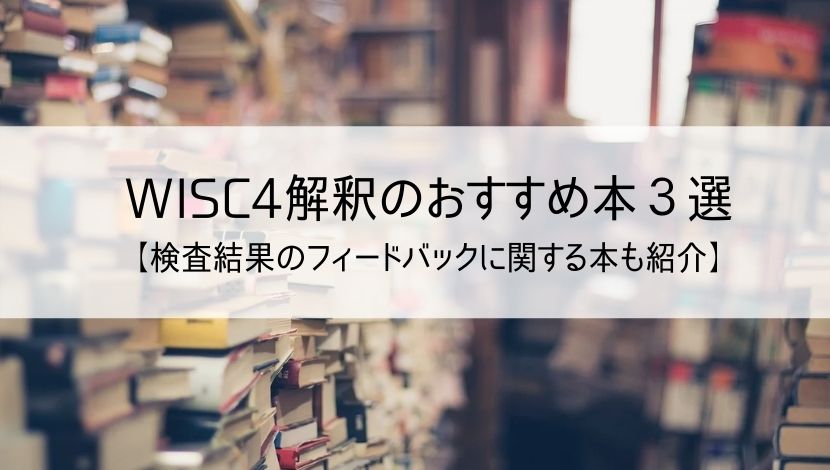大学の授業でアイデンティティ・ステータスの4分類を教わったけど思い出せない… そもそもアイデンティティってどういう意味だったっけ?
このような疑問にお答えします。
本記事の内容
- アイデンティティ・ステータスとは
- アイデンティティ・ステータスの4類型
- アイデンティティについて本格的に学ぶための鉄板書籍+学生特権
私は児童精神科で青年期のクライアントさんのカウンセリングをしていました。
大学時代に発達心理学・青年心理学の講義を取り、アイデンティティについて学んでいた身です。
そんな私が解説いたします。
おさらい,アイデンティティとは?
アイデンティティという言葉は元々E.エリクソンという発達心理学者が提唱した「漸性発達理論」(epigenetic theory)という発達理論に含まれる青年期の発達課題の1つです。自分らしさの感覚のことであり「自己同一性」、「自我同一性」などと訳されています。より詳しく知りたい方は
>>心理学的な「アイデンティティ」の意味:エリクソンの漸性発達理論をご覧ください。
アイデンティティ・ステータスとは
アイデンティティ(エリクソンで有名)は達成までの間にいくつかの特徴的な状態があり、その分類をアイデンティティ・ステータスと言います。
元々はマーシャ(J.E.Marcia)が提起した概念で、青年期の発達課題であるアイデンティティ確立に向けて、課題をどのように対処し克服しようとしているかの行動類型です。アイデンティティの「達成状況パターン」と言うこともできます。
アイデンティティ・ステータスの話に行く前にマーシャがどのように分類したかだけ説明させてください。アイデンティティ・ステータスは「危機(crisis)」と「積極的関与」いう2つの要素を測定し、それらがどのような状態にあるかでステータスを分類しています。
危機(crisis)
役割の試みと意思決定期間、と解説されていますが、ようするに、達成に向けて悩んでいるか否かです。
積極的関与(commitment)
人生の重要な領域(生き方・職業・価値観など)に積極的に関与しているかどうかです。
以後の内容は危機と積極的関与の2要素を頭に入れたうえで読むと理解しやすいと思います。
アイデンティティ・ステータスの4類型
アイデンティティステータスには拡散、早期完了、モラトリアム、達成の4つの分類があります。
1. 拡散(Diffusion) [ 危機:ありorなし/積極的関与:なし ]
危機の有無にかかわらず、積極的な関与ができないグループです。
自分の人生について主体的な選択ができず、何がやりたいのか分からない、途方にくれている感じです。
ことばにすると「一生懸命なんてダサいっしょ」といったイメージです。
・パターン1
自分自身について真剣に悩んだ事がないため、今の自分が良くわからないでいるタイプ。
・パターン2
全ての事に積極的に関与する事を回避し、無関心の状態を維持することで、あらゆる可能性を持っておこうとするタイプ。1つのことに打ち込むことで、現実の自分や自分の限界があらわになってしまうために起こる。
いずれにしても自己評価は動揺しやすく、他者との親密な関係を形成できずにいることが多いと言われています。他にもむさしさ、自意識過剰、偶然に身を任せるといった特徴があります。
2.早期完了(Foreclosure) [ 危機:なし/積極的関与:あり ]
危機を経験していないのにも関わらず、積極的関与をした結果、一見すでにアイデンティティが確立されたような状態のグループです。
「これでいいや。簡単そうだし」などと生き急そぎ、重要な選択を熟慮せずにしてしまった方とも言えます。会社社長のご子息に多いかもしれません。
特徴として、両親とは密着した関係にあり、その考えや価値感を身につけています。職業の選択にも親が積極的に関与しているので、一見アイデンティティが達成されたように見えますが、その価値観は吟味なしに無批判で身に着けたものであり、見せかけです。
結果的に心理的な悩みや危機をあまり経験しておらず、考えも硬く融通がきかないため、自分の価値観が通用しないような状況に置かれると混乱し防衛的な行動をとります。
3.モラトリアム(Moratorium) [ 危機:最中/積極的関与:あいまい ]
エリクソンは心理的・社会的な責任の猶予期間のことをモラトリアムといいました。経済用語のモラトリアム(支払い猶予期間)からきています。
そのモラトリアム的な生き方をしているグループをマーシャがモラトリアムと分類しました。このグループは大人なるために必要な自分の適性や価値観を探求している、つまり危機を経験しつつある群です。
「自分はいったい何がしたいのだろう、あれかな、これかな」などと悩むイメージです。
自己定義を得ようといろいろな事に関心を持ち、積極的に関与しようと試みるが、それがあいまいで焦点が定まらずに悩むといった行動が見られます。
ですがこのモラトリアムにも2つのパターンがあるといわれています。
1.ネガティブなモラトリアム
関与の対象を探そうとしているものの「明日できることは今日しない」ような楽に生きようとする人。モラトリアム人間と呼ばれていた人たちです。
2.ポジティブなモラトリアム
将来どのような人間になりたいかはわからないけど、1つには絞らず、目の前に興味のあることがあるからそれに打ち込む人。結果として職業が後からついてきたりする。大器晩成の要素をもっているような人です。
4.達成(Achievement) [ 危機:あり(あった)/積極的関与:あり ]
危機を経験し、それを通じて自分で選択した人生のあり方に対して積極的に関与をしているグループです。
つまり、自分なりのアイデンティティをそれなりに確立している人たちです。
自分についてこれまで悩んだ経験がもとになっているので、何ごとも自分の意思で選択し、それに積極的に関与しようとする姿勢を持ち、かつ柔軟に対処できるのが特徴です。他のステータスに比べて自己評価は高く、親密な人間関係の形成が可能であると言われています。
私が授業を受けたときに先生が言っていましたが、「青年期ではまれ!」だそうです。
以上4つのグループを紹介いたしました。アイデンティティ・ステータスのイメージをつかめていただけたでしょうか?
アイデンティティは最終的には達成に向かっていくという性質をもっているらしく、達成以外の3グループは達成に至るまでのバリエーションととらえることもできそうです。
アイデンティティについて本格的に学ぶための鉄板書籍
以下の大野先生の書籍がアイデンティティ・ステータスの理解に非常に役に立ちます。読み物としても本当に面白く、「愛」について心理学的に論じている数少ない書籍だと思います。
本ブログでは他にも心理学に関するコラムを執筆していますので、ぜひご覧ください。

精神分析
2022/4/16
【具体例】価値下げ・理想化・否認・投影・合理化・投影性同一視・行動化・受動攻撃|自我の防衛機制2
精神疾患の診断マニュアルであ「DSM-IV」の付録には、様々な防衛機制が7つの「水準」に分けて掲載されています。※今後の研究のために提案された軸として「付録」として記載されています。 この記事では7つの水準のうち「イメージの軽度歪曲の水準」「否定の水準」「重度のイメージ歪曲の水準」「行為的水準」「防衛制御不能水準」の中から「価値の引き下げ」「理想化」「否認」「投影」「合理化」「投影性同一視」「行動化」「受動攻撃」を紹介します。 前回記事は以下です。 【具体例】昇華・ユーモア・抑制・置き換え・ …
ReadMore

性格心理学
2022/4/16
【血液型性格診断の元祖】性格の類型論とは?【ガレノスの4気質説】
皆さんは「自分の性格を説明してください」と言われたときにどう答えますか? 「やさしい」や「おおざっぱ」などの特徴を伝えるでしょうか、それとも「誰々のような性格」や「A型っぽい」などカテゴリーに分けて伝えるでしょうか。性格心理学では前者を「特性論」、後者を「類型論」と呼びます。この2つが性格(パーソナリティ)心理学の基礎になります。 この記事では「類型論」を紹介します。特性論については以下の記事をご覧ください。 性格の【特性論】とは|オールポートの言葉の仕分けがルーツ 性格の捉え方は大別すると「特性論」と「 ...
ReadMore

臨床心理学
2022/3/6
老年期来談者への臨床心理的支援
“老年期”、“様々な喪失”、“老年期のクライアントへの臨床心理学的支援” について要点をまとめています。 ※この記事は大学のテスト対策、大学院入試の対策用の記事です。 老年期の心理的問題 65歳から75歳までを前期老年期とし、社会的役割からの解放が主な出来事となる。 75歳からを後期老年期とし、身体の衰えや、死へのプロセスの経験が起こる。 前期の人であっても、後期の出来事を経験することがある。 E.エリクソンによれば、老年期ではネガティブなプロセスばかりではなく、自分が生きてきた文脈の中で自分を受け入れ、 ...
ReadMore

精神分析
2022/2/19
【3分で読める】エス・自我・超自我とは|フロイトの心的構造論
今回はフロイトが提唱した心の仕組みである「心的構造論」をご紹介します。単に「構造論」とも呼ばれる精神分析の前提となる重要な概念であり、心は「エス(イド)」「自我」「超自我」という3つの領域からなるというのが要点です。 3分で読める程度に短くまとめてありますので参考になれば幸いです。 心的構造論とは(エス、自我、超自我) フロイトは人の心をエス(イドともいう(id, Es))、自我(ego)、超自我(super-ego)の3つの領域からなる1つの装置(心的装置)と考えていました。 これを「心的構造論」と言い ...
ReadMore

家族心理学
2022/4/16
オルソンの家族円環モデル:凝集性、適応性、FACESⅢとは
「皆さんは自分の家族がどんな家族か説明してと言われてうまくできますか?」 大人しいとか、良くしゃべるとか、意外と表現が難しいのではないでしょうか。 今回は家族心理学から家族機能の最も有名なモデルである「オルソンの家族円環モデル」とその評価尺度である「FACESⅢ」を紹介します。 オルソンの家族円環モデル 家族円環モデルは家族の機能を「凝集性」と「適応性」という2つの次元で決めるものです。なお、オルソンは提唱した人の名前です。 凝集性とは 家族メンバーの相互の情緒的結びつきのことを「凝集性」と呼びます。情緒 ...
ReadMore

恋愛心理学
2022/4/16
運命の赤い糸は20本ある説
運命の赤い糸とは? 運命の赤い糸とはご存じのとおり、自分と生涯のパートナーとを結ぶ見えない糸があるという伝承です。wikipediaで調べてみたのですが、アジアでは結構古くからある伝承みたいです。 この概念には運命の赤い糸は1本であるという前提があります。 この”1本の赤い糸”、つまり運命的な出会いは生涯に1回しかない、という思い込みがパートナーの選択を困難にしているという考えがあります。 例えば赤い糸が1本であると考えた場合、良い人に出会う度に「この人で良いのだろうか、もっと良い人がいるかもしれない」と ...
ReadMore

家族心理学
2022/4/16
【家族ライフサイクル理論】家族の発達段階と課題とは
※この記事は大学時代のノートです。 人間個人に発達段階やそれに応じた課題があるように,家族にも発達段階や課題があるとして提唱されたの家族ライフサイクル理論です。 一般的な家族が共通して経験するものであり、ある程度は予測可能なものだと言われています。 課題に適切に対処できない場合,特定のメンバーの問題行動につながったり、関係性が悪化する危険がありますが、適切に対処できた場合は家族関係がより親密になったり,家族としての成長につながる可能性もあります。 では実際にその段階と課題を見ていきましょう。 ...
ReadMore

精神分析
2022/2/24
【3分で読める】フロイトの局所論|意識・無意識・前意識
以前精神分析の前提として無意識の存在がある、ということを書きました。 今回はその無意識を含む人の意識領域について、精神分析ではどのように考えられているのかを紹介していきます。 意識と無意識(consciousness and unconsciousness) 精神分析のテキストではしばしば意識領域を氷山に例えて説明しています。 氷山の見えている部分は全体の一部分であり、大部分が水面下にあります。この見えている部分が私たちが自覚できる「意識」であり、水面下の大部分が「無意識」に例えられます。 心の大部分は普 …
ReadMore

精神分析
2022/2/19
防衛機制とストレスコーピングの違い
自我はエスから生じる「欲求」と超自我から生じる「理想や現実的制約」を調整する役割をもちますが、その調整する際に生じる不安や葛藤に対処して自我の安定を保とうとする機能は「防衛機制」(Defense Mechanism)と呼ばれています。 この記事では防衛機制と似た概念であるストレスコーピングの違いについてご紹介します。 防衛機制とは フロイトは自我は不安を「危険を予知する信号」として知覚し、そこで防衛機制を働かせると言っています。不安だけではなく、欲求の高まりによって生じる不快感、罪悪感、恥などの情緒体験に ...
ReadMore

家族心理学
2022/4/16
離婚を予測する4つの会話は非難・軽蔑・自己弁護・無関心|ゴットマンの夫婦研究
今回は夫婦関係の研究で非常に有名なGottman(ゴットマン)の「離婚を予測するコミュニケーション」についてです。 このゴットマン先生、夫婦研究ではかなり有名で、数多くの夫婦研究を行っています。私も修論で引用しました。もう夫婦の研究はゴットマンによってやりつくされたのでは?と思うくらい貴重な知見がたくあんあります。 今回はその中でも有名な離婚を予測するコミュニケーション(非難、軽蔑、自己弁護、無関心)を紹介します。 Gottmanの夫婦に関する実証研究のまとめ Gottmanは25年に渡る縦 …
ReadMore