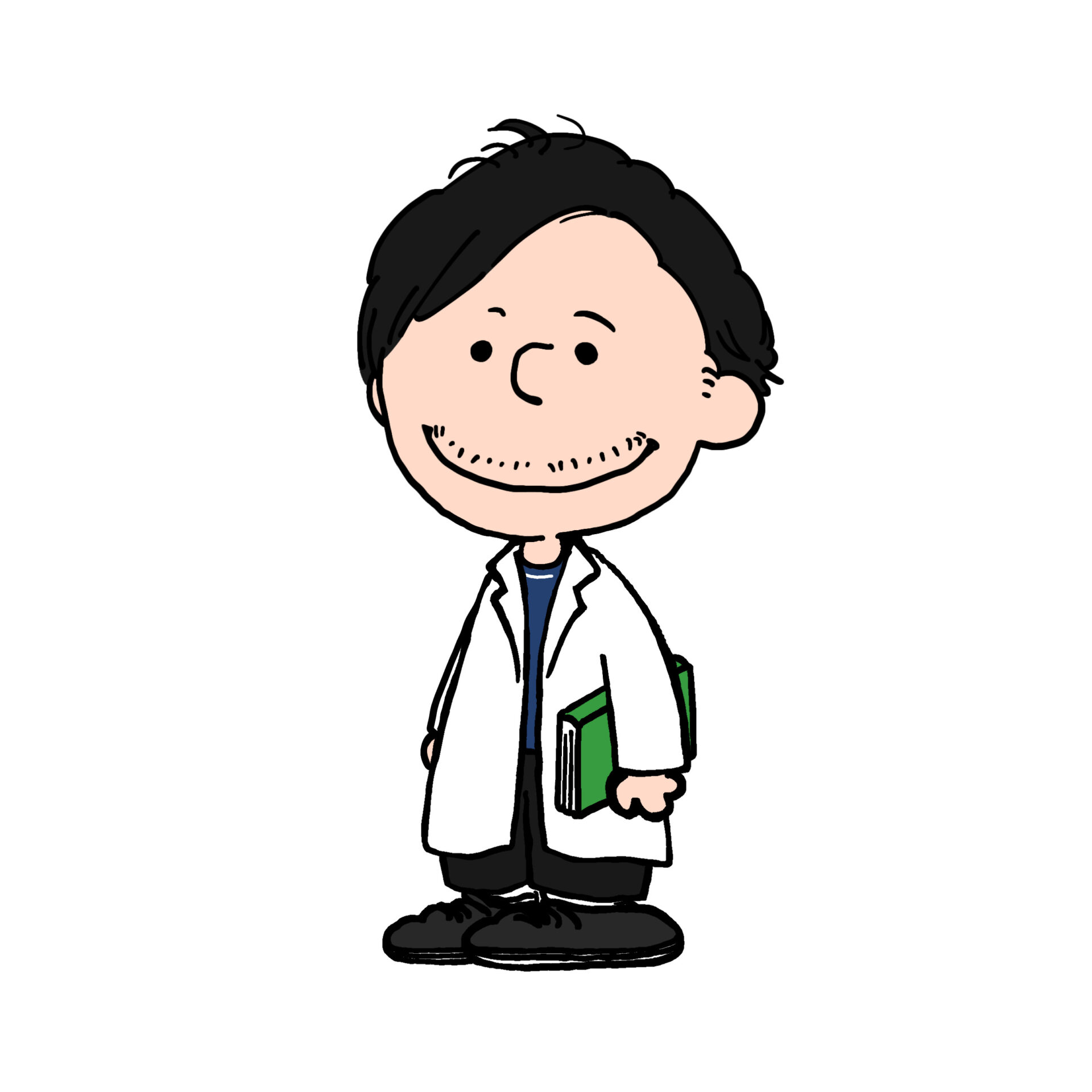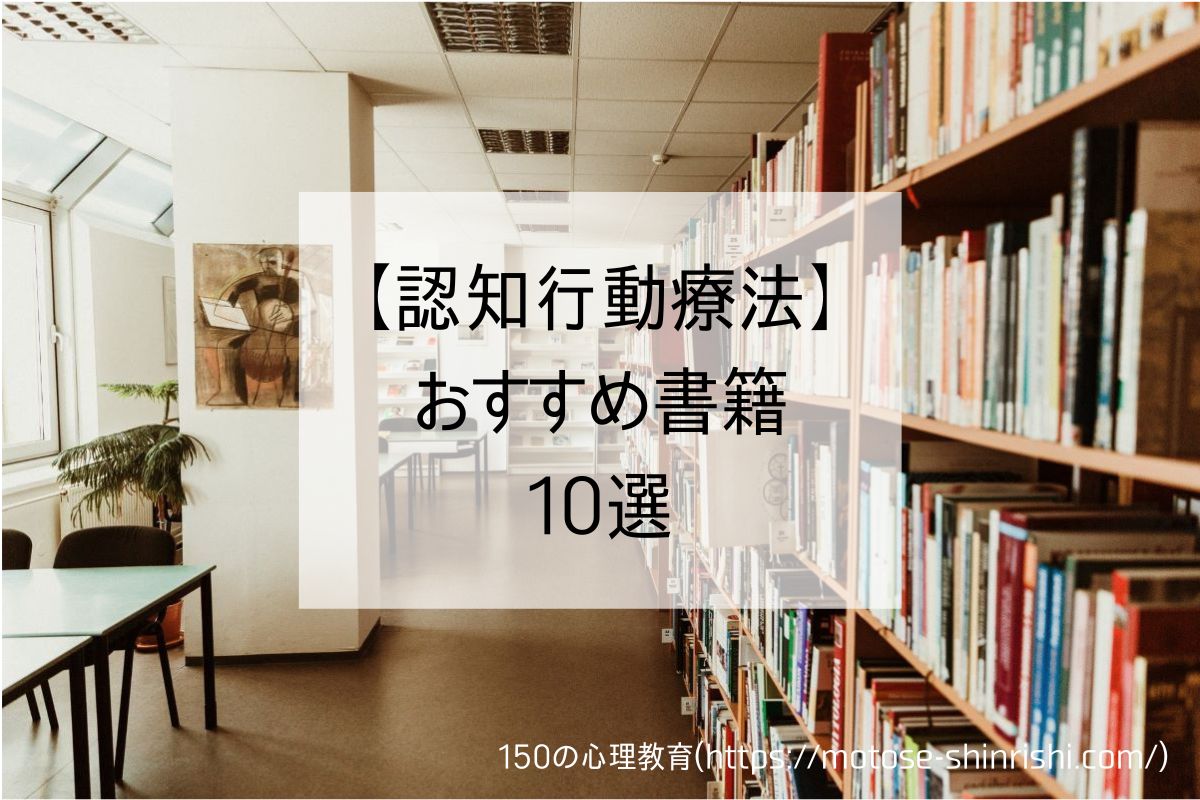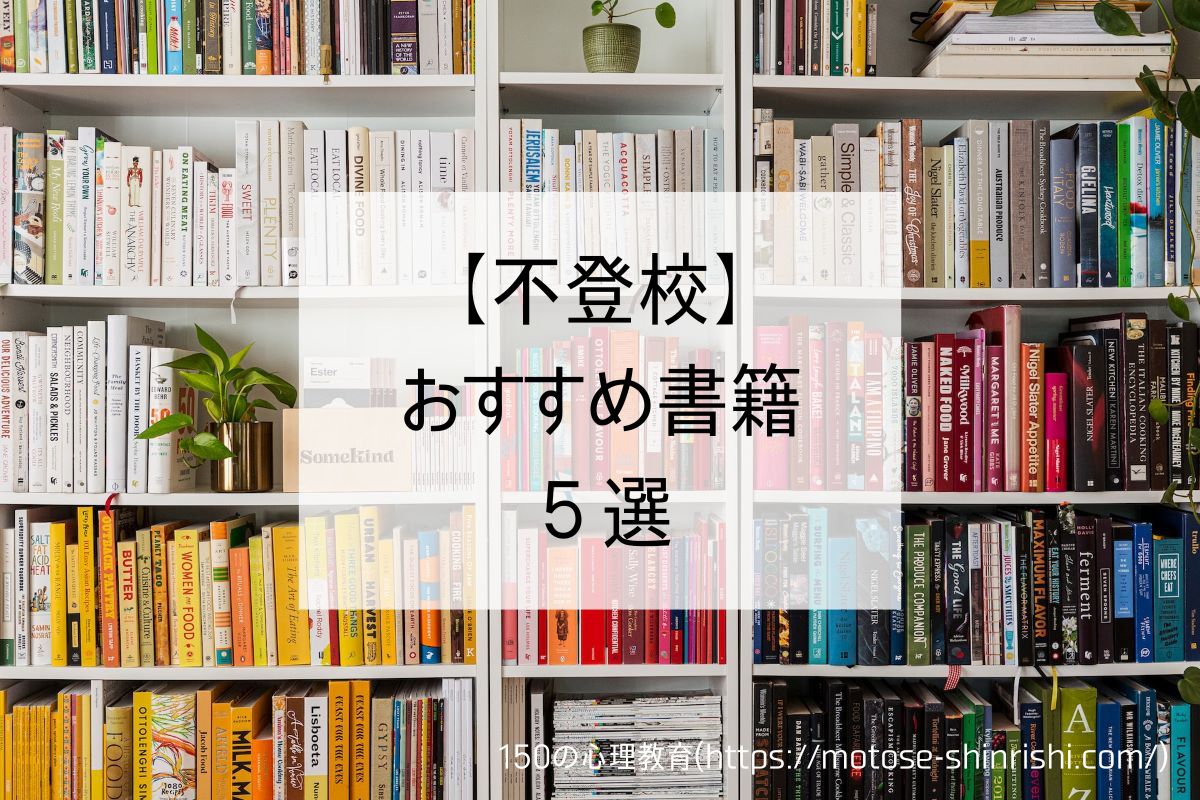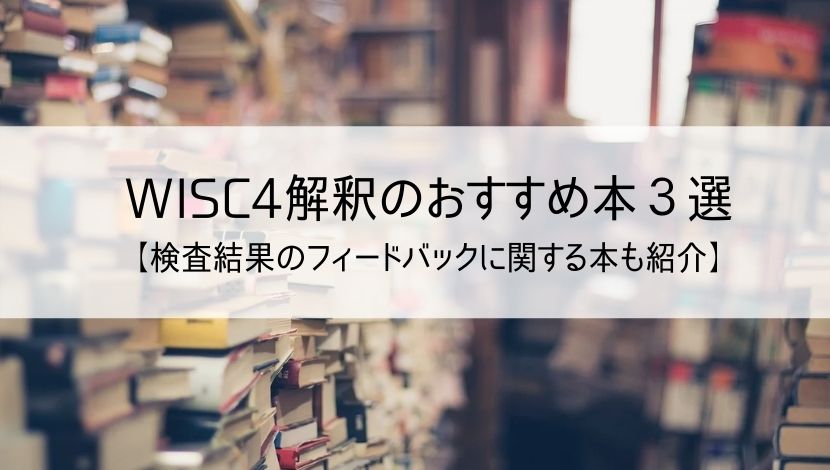このように考える不登校児童のお父さんは多いのではないでしょうか。
お父さんは日中は家にいないことが多く、お子さんの生活の様子を知らないことも多いと思います。
この記事ではお父さんだからこそできる不登校のお子さんや奥様への支援、大げさに言えば父親の役割についてお伝えしていきます。
本記事の内容
- 父の役割1:助言なし、指導なしで話を聞き、受け止める
- 父の役割2:母の味方になり、愚痴を聞く
- 父の役割3:母から聞いた「子どもの良いところ」をお子さんに伝える
超重要なので先に言いますが、不登校のお子さんにとってお父さんが受け止めてくれることはお父さんが想像する100倍はお子さんを元気にします。
ご自身も父親に認められたときに嬉しかったことはないですか?
逆に父親に認められないことで反発したり、意固地になったことはないですか?
それだけお父さんの力は不登校の助けになります。
対応は普段の家族仲によって効果・逆効果が変わる可能性があります。現状うまくいっているのであればいつも通り接してあげてください。
父の役割1:助言なし、指導なしで話を聞き、受け止める
お父さんというのは怖いとか、ちょっととっつきにくい印象を持たれやすいようです。
なんでそうなるかはここでは一旦置いておいて(なっちゃったものはもうしかたないので)、お子さんへどう対応するかです。
そんな怖いイメージのお父さんでしたら、話を受け止めて聞いてあげるだけでも相当な効果を発揮するでしょう。
イメチェンというか「父上、話わかるやないですか」とお子さんがびっくりすること請け合いです。
お父さんと話せたというのはなぜか自信になるお子さんもいますし、きっと元気が出ます。
具体的には、特に細かいことは置いといて、雑談してみてください。
否定せず、助言せず、話を広げて、「こういうことなんか?」と時々要約して確認し、お子さんの「そうそう」という「イエス」を引き出すように話しましょう。
これを専門的には「イエスセット」と言います。
イエスセットの例
- (父)このゲーム好きなんか?
- (子)そうそう。
- (父)どんなゲームなん?
- (子)これこれこういうゲーム。
- (父)こうこうゲームなんだ
- (子)そうそう。
- (父)面白そうだな。
- (子)面白いよ。
- (父)このキャラかっこいいな
- (子)そうでしょ。
- (父)キャラもかっこいいし面白いからハマるんやな
- (子)そうそう。
こんな感じです。
恐らくお父さんとしては、
「ゲーム何ていつまでやるんだ」
「勉強もしろよ」
「こんなんやってるから学校行けないんじゃないの」
などと思い浮かぶでしょうけど、言っても再登校のためにあまり効果はないです。
お父さんに助言なし、指導なしで話を聞いて受け止めてもらえることで、お子さんは元気がでます。
父の役割2:母の味方になり、愚痴を聞く
結論、お子さんに対処する前にまずお母さんの愚痴を聞いてあげてください。
そして、何を言われても上記のようなイエスセットを使い「そうそう」と言えるようにしてあげてください。
これはもうタスクとしてやって欲しいのですが「大変だったね」「ありがとう」と労ってあげてください。
奥さんに対するイエスセットの例
- (夫)今日は○○(お子さんの名前)どうやった
- (妻)いつもと変わらんよ
- (夫)というと?
- (妻)ゲームとかスマホ
- (夫)そんなん見てたら大丈夫かなって思っちゃうよな
- (妻)そうね
- (夫)疲れてるだろう
- (妻)そうね
- (夫)大変だったね
- (妻)そうね
- (夫)いつもありがとうな
- (妻)うん。
ここで奥様(母)が「あんたが協力してくれないからでしょ!」と逆ギレしてきてもショックを受けずにむしろラッキーと思ってください。かなりのボーナスです。
なぜなら、お母さんはとにかく不安や不満を心の内に溜め込んでしんどくなっていることが多いので、逆ギレでもなんでも発散させてあげてください。
もし逆ギレされたら、ただただ「そうか」「そうなんだな」と受容的に聞いてあげてください。
「じゃあどうして欲しい?」と聞いても良いですが、ヒートアップしているときに聞いても非現実的だったり、「そんなの自分で考えろ!」と言われるかもしれないので冷静になった後が良いかもしれません。
奥様の味方になるのとは反対に、お子さんと手を組んで奥様を敵に回すこと絶対にやってはいけません。
例えば母が怒っているときに子どもに向かって「お母さんこわいねー」などと言い、子どもと父が連合して母と対決するような構図を作るのは母を孤立させてしまうのでやめましょう。
母への支援はお子さんへの支援と同じ意味を持つということだけは覚えて帰っていただきたいです。
父の役割3:母から聞いた「子どもの良いところ」をお子さんに伝える
これはお子さんを褒めるバリエーションの1つです。以下の記事を参考にしてみてください。
一例としては、母から子どものほめたい行動を聞いておき「昨日お母さんが○○のここがすごかったんだよって言ってたよ」等とお子さんに伝えるのです。
これには、
①お母さんがちゃんと見てくれている、
②お父さんが褒めてくれた(と子どもは感じる)という一石二鳥の効果があります。
以上3点をお伝えしてきました。
これができたらお父さん、文字通りヒーローです。家庭を助けてあげてください。みんな待ってますよ。
他にも不登校に関する記事がありますので、よかったら参考にしてみてください。お気に入り登録やtwitterのフォローもお待ちしています。