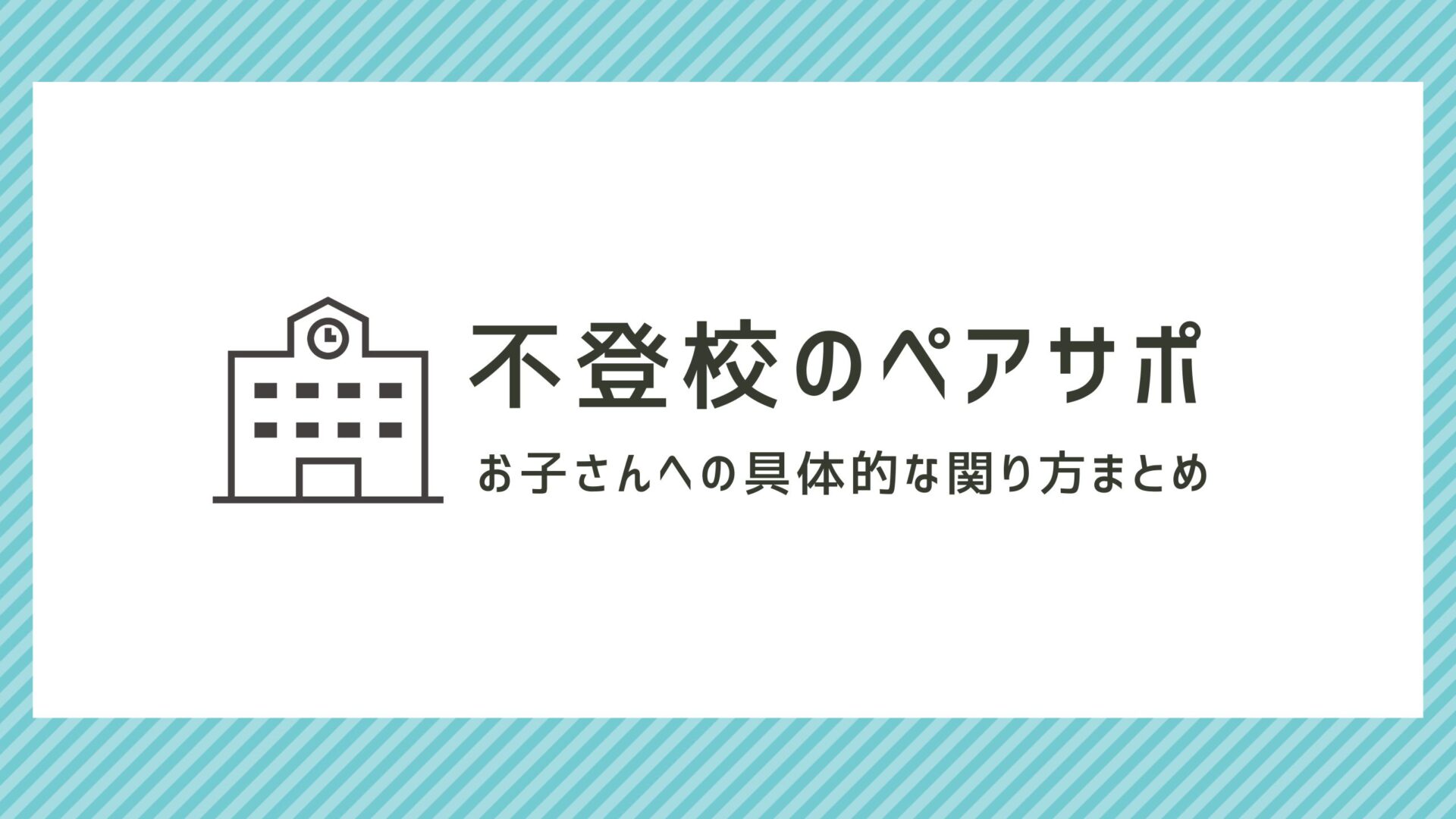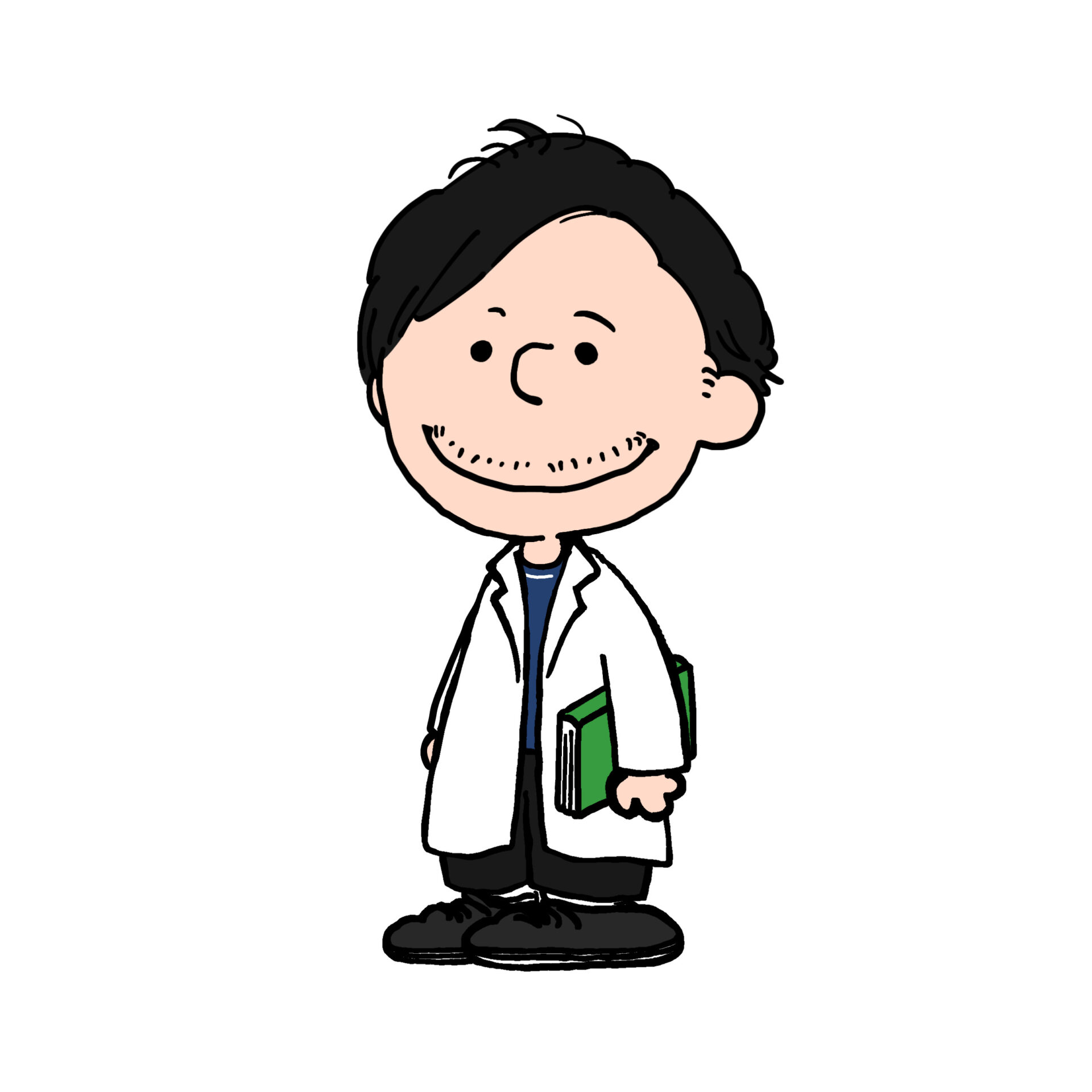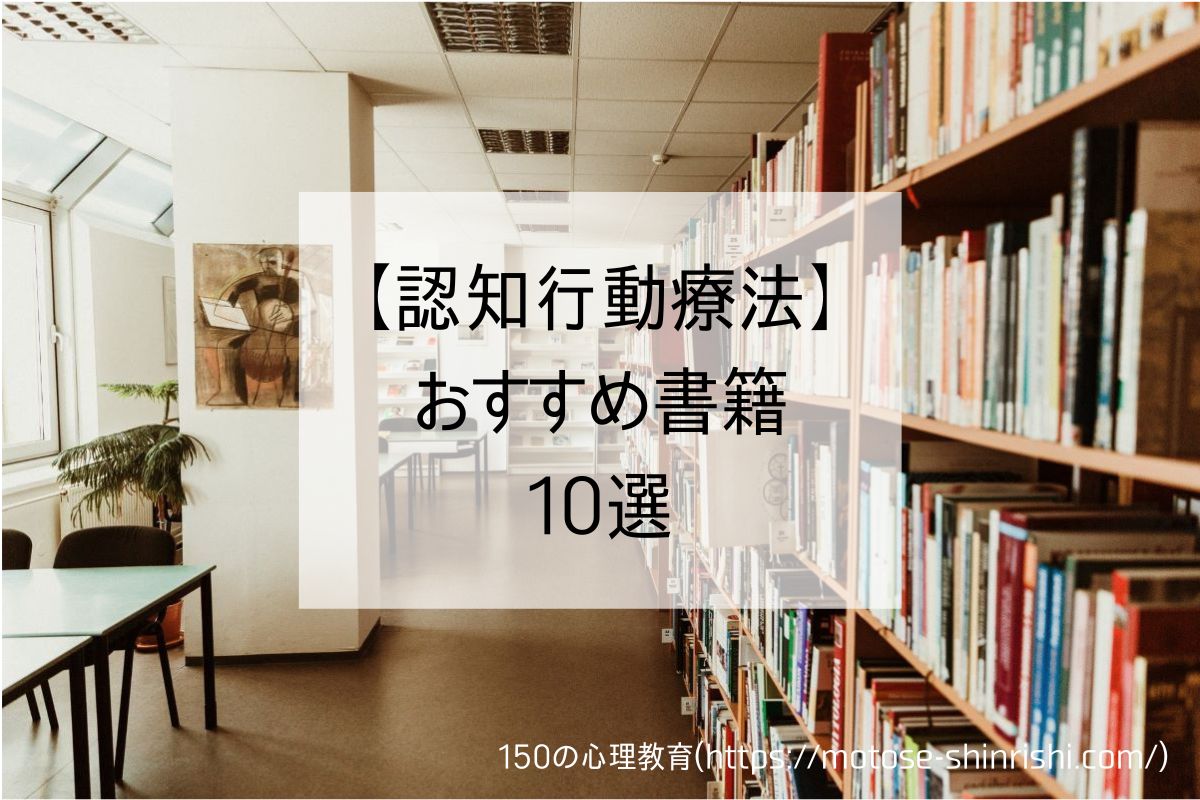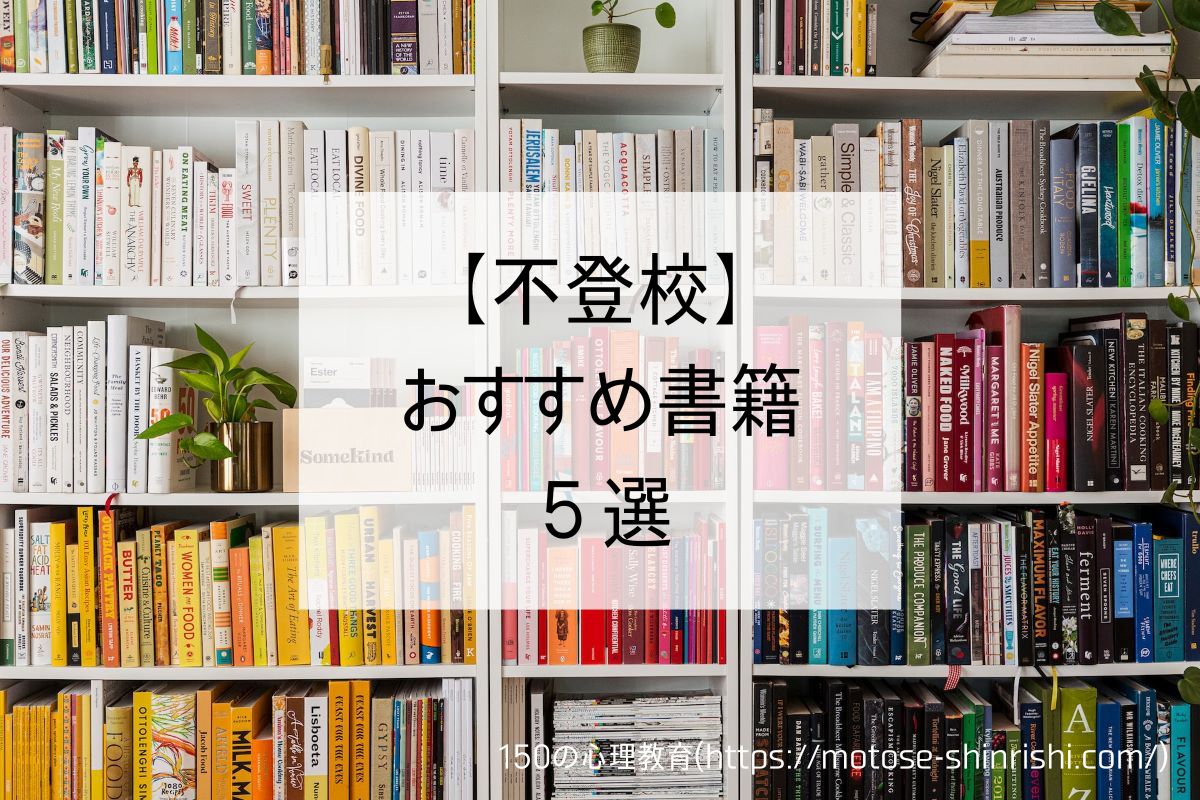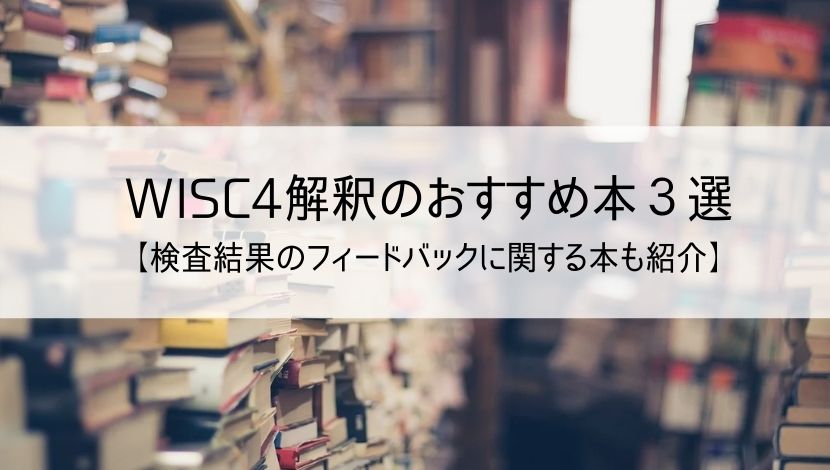母親の私だってもう疲れた…。このままうつにでもなったらどうしよう…。
こういった疑問にお答えします。
本記事の内容
- 不登校の母親が疲れてうつにならないためにできること【ある母の言葉】
- 何に疲れたのか解説します【少し元気になってから読んでください】
- 実はたくさんある。子どもが23歳になったときの解決像
私は児童精神科や学校で不登校のお子さん・親御さんのカウンセリングをしていた臨床心理士です。
お母様が疲れてしまう理由は「このままではうつになっちゃうよ」と思うくらい、お子さんのことを熱心に考えてあげているからに違いありません。
ご家庭ごとに色々な考え方ややり方がありますが、共通していることは心からお子さんのことを考えてあげていることだと、カウンセリングをしていて感じます。
熱意があるがゆえに精神的にすり減ってしまうのは何とも切ないことです。
本記事では親御さんの疲れが少しでも軽くなる方法を実際の親御さんの体験談をもとに紹介します。
その後、もし疲れが少しとれて「私はいったい何に疲れたのか」と振り返れるようになったら、2章の「疲れた理由」の分析を読んでみてください。
最後に少しでもお子さんの将来の見通しが持てるように、もしお子さんが23歳(大学卒業後の年のことです)になったらどのような解決像があるのかを紹介して終わりたいと思います。
不登校の母親が疲れてうつにならないためにできること【ある母の言葉】
私が実際に、不登校のお母様から聞いた印象的な言葉を紹介します(ブログ掲載にあたっては許可をとっています)。
「無理に行かせたり、待ってみたり、いろいろなことを試して、今すぐどうにもならないことはわかっていたんです。だから、ただただ、共感して欲しかったんです」
この言葉を聞いてわかったことは、このお母様が望んでいたものはお子さんを学校に行かせる方法ではなく、自分を受けとめてくれる相手だったということです。
受けとめてもらうことで、日々を生活する気力をぎりぎりでもキープすることができたのだと思います。
では、現代において不登校の親御さんが共感をしたりされたりする方法を3つ紹介いたします。
既に試していることもあると思いますが、その時はその方法をぜひ続けてみてください。
- SNSで不登校の親御さんとつながる(注意点もあり)
- 親の会に行ってみる
- カウンセリングを受けてみる
1つずつ解説していきます。
1. SNSで不登校の親御さんとつながる(注意点もあり)
SNSをやっていない親御さんは始めてみるのもよいかもしれません。
なぜなら、多くの同じ悩みをもった親御さんに出会うことができるからです。
私の知り合いも、1人じゃないんだなと思ったと言っていました。

と感じた方もいるでしょう。
確かに、そういった方がいないとは言い切れません。
また、「子どもが学校に行った」という成功ツイートや、私のような支援者が「対応方法はこうです」と言った助言ツイートも出てきてしまう可能性はあります。
良し悪しを考えて、自分に合うと思ったら使ってみてもいいかもしれません。
2. 親の会に行ってみる
Xのような顔の見えない関係や何が出てくるかわからないSNSに抵抗がある親御さんは「不登校の親の会」を利用してみるのも1つの手です。
理由はtwitterと同じで、同じ悩みをもった親御さんとつながることができ、共感し合ったり、お子さんへの対応の工夫をシェアできるからです。
以下のページは全国の親の会をまとめてくれているので参考になります。
>>【随時更新】全国の不登校・親の会一覧(外部サイト)
3. カウンセリングを受けてみる
同じ悩みをもった方と話すのは気が引けるという方は、カウンセリングを受けてみるのも1つの手です。
金銭的な負担を考えると無料で受けたい方もいるかと思います。
その場合は市町村の教育支援センター(教育委員会)が行っているカウンセリングを利用するとよいかと思います。
教育支援センターの職員は元教員や臨床心理士など専門的な知識を持った方ですから、安心して相談することができるはずです。
そのとき、まずは共感して話を聞いて欲しいとお伝えできるとよいでしょう。
向こうもよかれと思ってお子さんへの関わり方を助言してくる場合もあるので先手を打ち、まずは聞いて欲しいというニーズをはっきり伝えることでリスク回避ができます。
わかって欲しいのではなく、具体的な対応方法を知りたい場合は私の書いた「不登校のペアサポ」が役に立つかもしれません。
一旦ここまでのまとめです。
不登校の母親が疲れてうつにならないためにできること。
- SNSで不登校の親御さんとつながる(注意点あり)
- 親の会に行ってみる
- カウンセリングを受けてみる
次の章では具体的に「何に疲れたのか」について、もう少し踏み込んでみたいと思います。
今はそんなこと知りたくない、という場合は少し元気になってから読んでみてください。
何に疲れたのか解説します【少し元気になってから読んでください】

結論から言えば、お子さんに気を遣うことに疲れたのではないでしょうか?
別の言い方をすると、我慢に疲れたともいえるかもしれません。
- ゲームばっかり、怒りたいし、正したいけど、我慢
- 勉強しろ!と思うけど、プレッシャーをかけないように我慢
- 学校行かないなら理由ははっきり言え!、言えないことはわかっているから我慢
よって、最初の一歩は、不登校のお子さんを学校に行かせようと躍起になるのではなく、行く行かないにかかわらず、家庭でお子さんに気を遣わずにコミュニケーションをとることかもしれません。
具体的には以下の視点が役に立つと思います。
- ほめるときはしっかりほめる
- 叱るときは適切にしかる
- 家庭のルールは明確にする。許すところ、許さないところをはっきりさせる
1と2に関しては以下の書籍が役にたちます。
私も持っていますが、叱ることを劇薬と捉え、使用することに慎重になっているところに非常に誠実さを感じます。
家庭のルールについては例えば朝起きる時間と寝る時間、日中の電子メディアの利用、もんげん、おこづかい、勉強などでしょうか。
学校行く行かないにかかわらず、一般的なスマホのルールなどは検索したら出てきますので参考にするとよいかもしれません。
生活リズムや日中のスマホやゲームの制限については親御さんがとる支援の方向性によって大きく2パターンに分かれます。
それについては以下の記事を参考にしてみてください。
>>【重要】不登校支援の結論をお話しします【後悔しない基本の知識】
最後に、これでお母様の気持ちが楽になるかはわかりませんが、生き方って色々あるよ、という気休め程度の章を書きましたのでお時間あれば読んでみてください。
実はたくさんある、子どもが23歳になったときの解決像
別の記事でも書きますが、次のことを想像してみてください。
もしここに、お子さんが23歳になった時の姿が見える水晶玉があったとしましょう(めちゃくちゃうさんくさいのは許してください)。
そこに映るあなたのお子さんが、元気に、自立して、働いていたとしましょう。
もしそうであれば、今学校に行かないことを全て許し、もうゲームでもなんでも自由にやってください、そう思えませんか?
気を遣わずに、言いたいことを言えるのではないでしょうか?
つまり、親御さんの願いは「学校に行って欲しい」のではなく、「大人になった時に自立して生活できるようになって欲しい」のではないでしょうか。
正社員で働いていないにしろ、自立して生活する方法はあります。
最後に、お子さんが23歳になったときの選択肢、ある意味で解決像を少し紹介して終わりたいと思います。
- 正社員で仕事をしていたら最高
- アルバイトでもまぁまぁ最高
- 内職でもしないよりはまし
- どうしても働くのはまだ無理だから、適応障害の診断をもらって就労移行支援を利用するなら希望がもてる
- 23歳の時点で専門学校や大学に行ってても全然OK
- どうしてもの時は障害年金や生活保護もある
「そんな確約はできないんだから、やっぱり不安」という親御さんもいるでしょう。
その場合、少し冷静になってこう考えてみてください「学校に行っていた人だって23歳で仕事していない人はいる」と。
私は成人のカウンセリングをしていて思うことがあります。
無理やり学校に行って傷ついて、大人になってもその傷が癒えずに自己肯定感が低く、次に踏み出す勇気がもてない方いるんだなと。
ある人が言っていたのは、私は学校に行っていたけど、学校に行っていない人を見ると「自分を守る強さがある」と思うと。
不思議なことにその人は学校に行っていたからこそ、不登校には「自分を守る」という前向きな意味があることに気づいたのです。
不登校のお子さんや親御さんからすると「そんなことはない」と否定したくなるかもしれませんが、見る人によってはそう見えるようです。参考になるかはわかりませんが、そう言っていた人がいるのは事実です。
本記事はここまでになります。他にも不登校関連の記事があるので、よかったら参考にしてみてください。