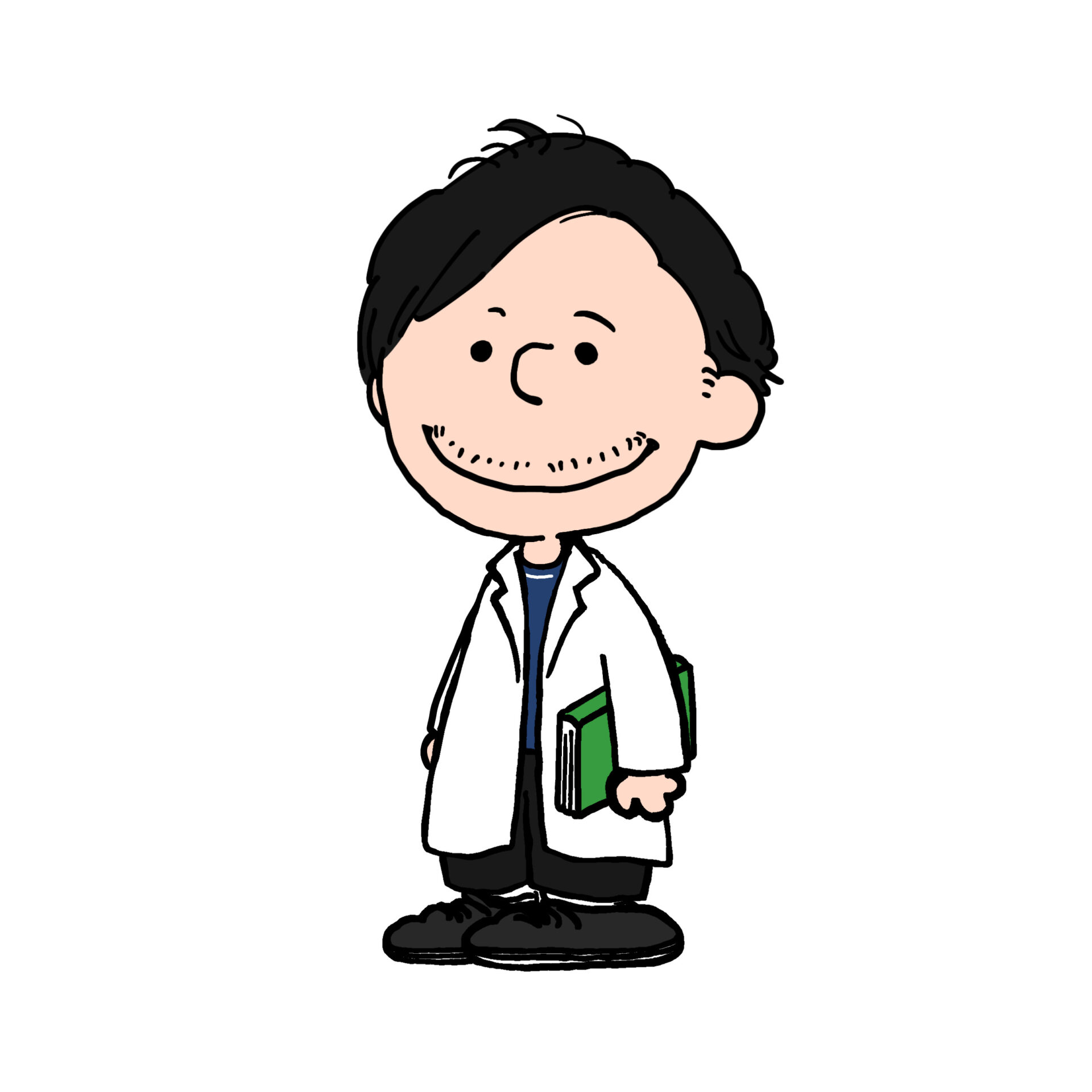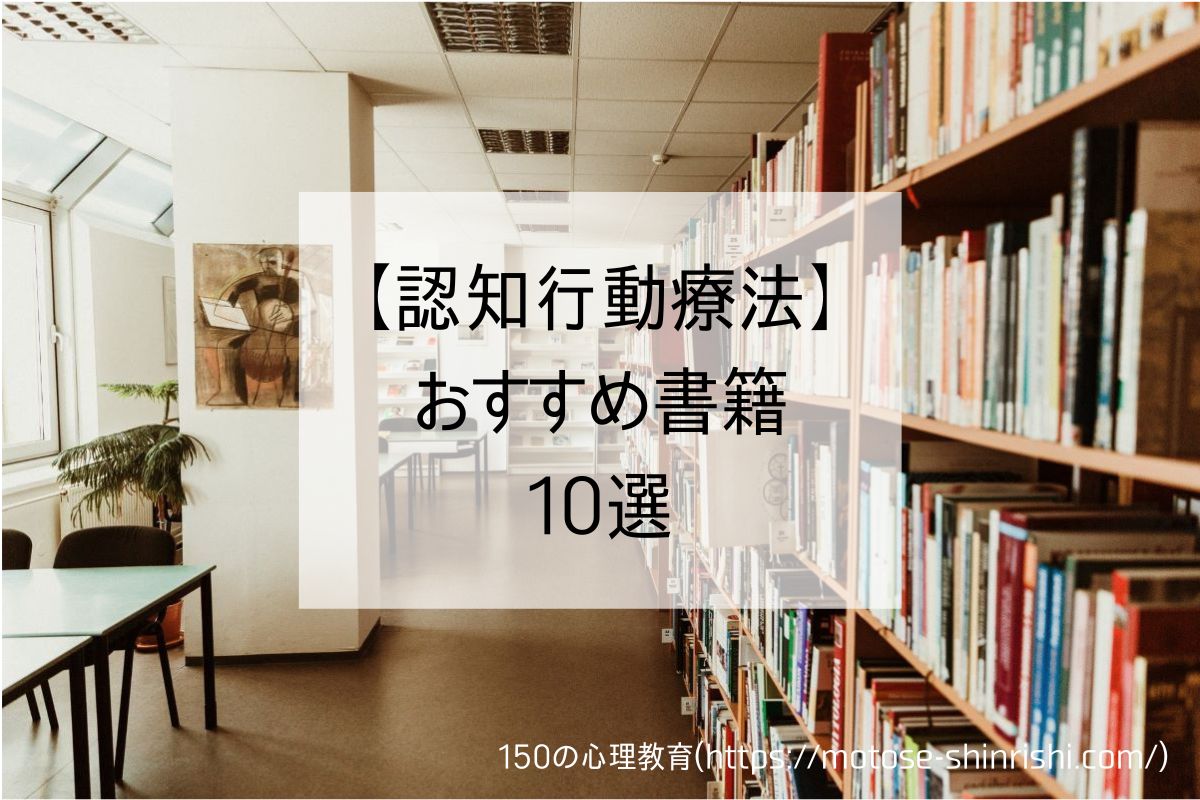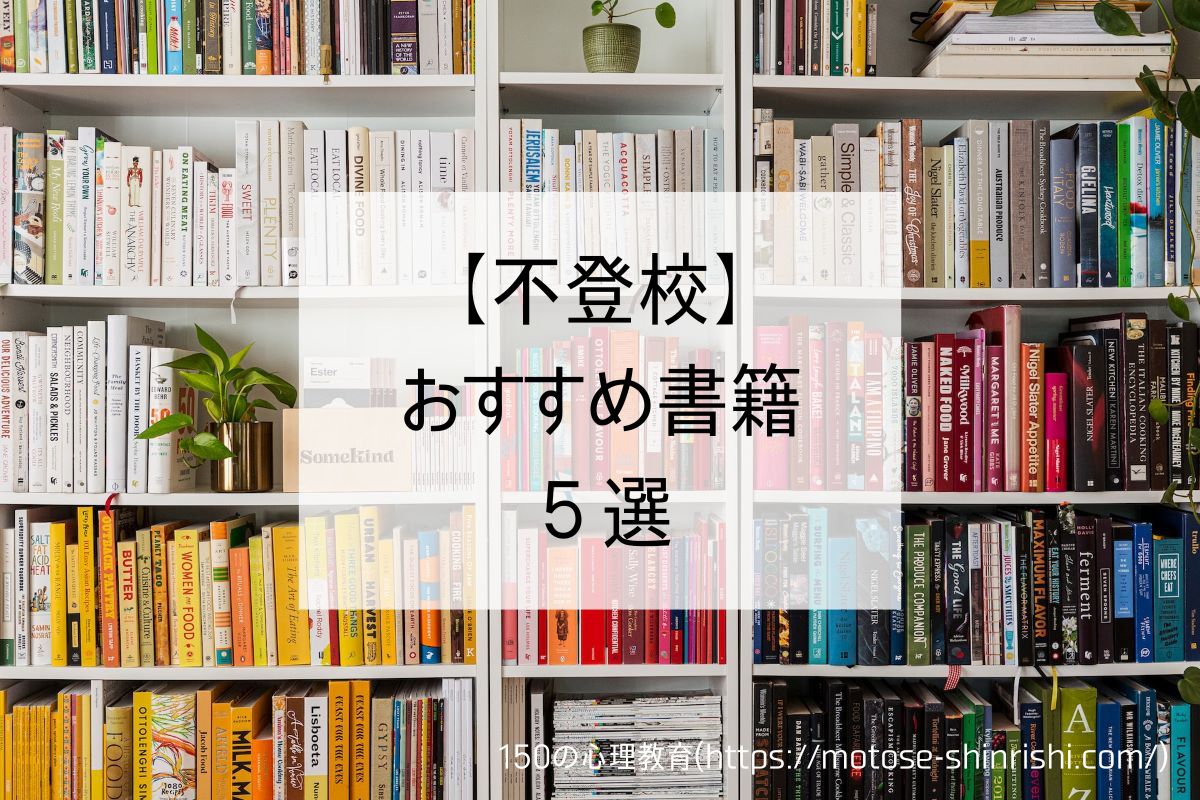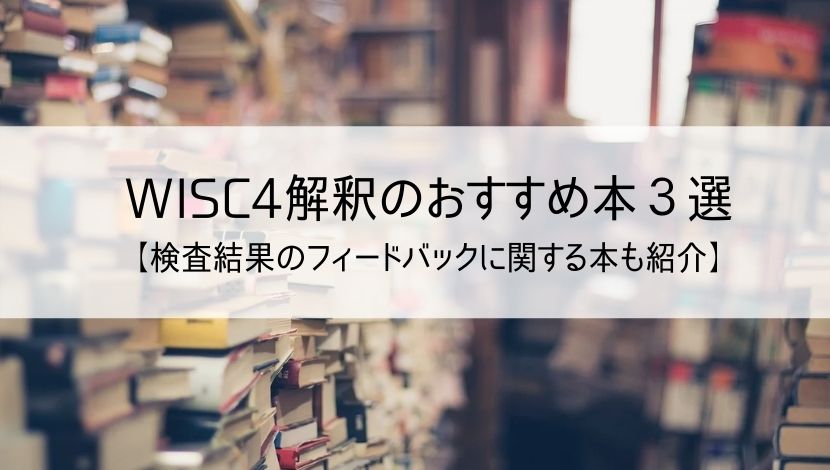こういった疑問にお答えします。
本記事の内容
- 不登校対応で、祖母がうるさいときに低ストレスで対応する方法
- 夫が祖母よりの考え方をしているときにどうしたらよいか
- 夫が発達障害で私はカサンドラ症候群かもしれないと思う方へ
私は児童精神科や学校でお子さんや親御さんのカウンセリングを行っていた臨床心理士です。
家族の理解がなかなか得られず協力体制が築けていないケースも対応してきました。
祖母が口うるさいと毎日がイライラしますが、味方になってもらえれば心強い協力者になる場合もありますので参考にしてみてください。
1.不登校対応で祖母がうるさいときに低ストレスで対応する方法
結論から言えば、祖母対応の型がわかっていないからストレスがたまります。
その型を覚えることで低ストレスで対応することができます。
対応の前に、まずどのくらい理解がわるいのかを見定めましょう。
度合いによってその後の戦略は異なります。
- 全くわからずやではなく、少し伝え方を工夫すれば味方として助けになってくれそうな場合
- 手のつけようのないほど理解がなく、改善が見込めそうにない
多くの場合は①だと思いますが、心理的DVなどがある場合は味方に引き入れることが困難なケースもあります。
その場合、児童相談所などしかるべき機関に相談して介入してもらう方が良い場合もあります。
ここでは①の場合を想定してお伝えします。
まず前提として、祖母に不登校を理解してもらうのは難しいことです。
なぜなら、祖父母の時代では不登校という現象がほとんどないからです。
よって、なぜそんなことになるのか見当もつかないし親の育て方が悪いに違いないとなりやすいのです。
また、一般的に祖父母は母よりもお子さんの養育に関与する比重が弱いため、優しいメッセージを送ることが多くなります。
お子さんは褒められたり、優しくされたりするとそこそこ良い反応するので、祖父母から見れば「孫は良い子で問題があるようには見えない」「だから悪いのは親である」という気持ちになりやすいようです。
心理的背景はこれくらいにして、どうやって関わるのが良いかその「型」である菜花先生の4ステップを紹介します。
以下がその4ステップです。
「不登校から脱け出した家族が見つけた幸せの物語」(菜花,2017)より引用
- 共感:ご家族の話(つらさ)をじっくり聴いて気持ちを理解してあげる
- 現状認識:ご家族の言葉で、あなたやお子さんが「どう感じているのか」を伝える
- 要望:これからはどう接して欲しいのか、どう接して欲しくないのか伝える
- 継続:改善されるまで1~3を繰り返す
私のこのやり方はよい方法と思っています。
なぜなら、祖母から見て自分の意見も聞いてもらえる安心感がありますし、具体的にどうしたらよいかわからない不安を解消してあげることができるからです。
1つずつ解説していきます。
ステップ1:共感
人は自分の意見を受け止めてもらってはじめて相手の意見を受け入れられることが多いものです。
まずは祖母の話を共感的に聞いてみましょう。
意見を聞くというというより、祖母の抱えているもやもやを全部吐き出せてあげるイメージです。
しっかり聞くことができたら、ぜひ自分にちょっとしたご褒美をあげてください。おつかれさまです。
ステップ2:現状認識
祖父母が心配のあまり悪気なくかけている言葉でお子さんが傷ついてしまうことや、お母さんが責められているように感じること、そのことで子どもにどんな影響があるのか、といった現状をできるだけ客観的に伝えましょう。
具体例:「学校は行った方が良いよ」とおばあちゃんに言われたけど、そんなことはわかっているしもう言われたくないと息子が言っていました。私も子どもが不安定になると対応にこまるのでしんどいです。
十分に共感ができていない場合など、祖母も反発してくることがあるかもしれません。
その時は売り言葉に買い言葉になるとまた面倒なので、お経だと思って聞き流しましょう。
感情的に喧嘩するよりはましです。
ステップ3:要望を伝える
しっかりと祖母の言い分を聞き、現状を認識してもらうことができると相手も「わたしがやっていることってもしかして良くないのかも」という気持ちが芽生えます。
要するに祖父母も自信がなくなってくるわけです。
そこで、どうしたら良いかわからないという相手の不安に寄り添い、具体的な要望を伝えましょう。
要望を伝える際の具体例
- 「気長に見守ってもらえると助かります」
- 「自信をつけることが大切なので、子どものよいところは小さなことでも褒めてください」
- 「子供を不安にさせたくないので、心配なときは子どもではなく私に相談してください」
要望を伝える際のコツ
コツは、とにかく具体的に行動レベルで伝えることです。
「~~してもらえると助かります」「~~されると辛いです」など、して欲しいこと、して欲しくないことを具体的にしてご家族ができるサポートの方法をハッキリ伝えると良いでしょう。
「~~だから~~してください(しないでください)」と理由を添えてお願いするのも理解が得られやすく効果的です。
ステップ4:1~3の継続
一度ですぐに変わらなくとも、継続して毅然と対応することで次第に理解してくれる場合もあります。
大切なのは「共感」→「現状認識」→「要望」の順番で伝えることです。
共感がないと相手も批判されている、責められていると感じて反発してしまいます。
お母さんも我慢が必要でむずかしいとはおもいますが、少しでも気が楽な毎日を過ごすために参考にしてみてください。
補足ですが、病的ではないけども、親の考え方を全否定してくる祖母への対応についても菜花先生が説明しているので紹介いたします。
全て否定してくる家族への対応
表面上は相手に同調し(肯定)、その意見は聞かずに自分の好きなようにやりましょう。
当然あとでその人は怒るでしょう、そうしたら「そうですね。怒りますよね。ごめんなさい」と素直に笑顔で「イエス」で返します。こんな具合に、Noマンへの返事は全て笑顔&イエスで返し、実際のあなたの行動は自分の思った通りにやるのです。これを繰り返しているとどうなるかというと、やがて諦めて何も言わなくなります。
「不登校から脱け出した家族が見つけた幸せの物語」(菜花,2017)より引用
ようするに、言葉の上では相手の意見を「はい」と聞いておき、実際の指示は無視するといういわば「開き直り」での対応です。
個人的には、この対応の肝は母(父)がお子さんへの対応の主導権を取ることだと思っています。
少し解説します。
指導する側とされる側がいた場合、指導される側が間違っている、という暗黙の前提があります。
「そんなことじゃ駄目よ」と言われて聞き入れていたら、主導権は祖父母です。
もちろん、本当に祖父母の言う考えが良いと思えたら取り入れたらよいです。
指示に従わずに自分が正しいと思う行動を続け、かつそれがお子さんや家族のためになっていれば、次第に批判する方がクレーマーであるという現実が構成されます。
そしたら相手は静かにするしかなくなりますので、上記のような対応が有効となります。
では次に、夫が祖母よりの考え方をしている場合の対応について紹介いたします。
2.夫が祖母よりの考え方をしているときにどうしたらよいか
これまで旦那さんにどうかかわってきたのかで対応は変わってくるかと思います。
日ごろからお母さんが旦那さんにガミガミと文句を言っていたのであれば、旦那は攻撃されているように感じていたかもしれません。
そういうときは、まずは小さな感謝を小出しにしていく、すると旦那さんは少しずつこちらの意見を聞く準備ができるかもしれません。
逆にお母さんが常に旦那さんの言いなりになっていたのであれば、毅然とした態度で自分がつらいこと、私に協力して欲しいこと、子どもにどういう悪影響がでているのかを説明した方がよいかもしれません。
旦那さんの性格、忙しさ、旦那さん自身の成育歴などさまざまな要素がからんできますので専門家に相談することも検討してみてください。
補足:不登校の父親の心理
夫の心理なんて知りたくないよ!という人はここは読み飛ばしてもらってかまいません。
多くの場合、父も父でどう対処したら良いかわからず混乱しており、仕事で疲れているので対応は妻に任せたいというのが本音だと思います。
もう少し男性心理を言えば、子どもの力にはなりたいけど母に「そんなことはもうやったよ」などと否定され、自分の無理解・無能さが露呈することを恐れているパターンは多いです。
結果として「家のことは君に任せる」と丸投げして責められることを回避するわけです。
妻の夫に対する働きかけが、意識的か無意識的かはわかりませんが叱責となり、夫の防衛を強くしてしまっているのです。
男性は自分の能力が劣っていたり無力だったりすることに敏感な傾向にあると思います。
ゆえに母から父に「○○へはこう対処した方が良いってカウンセラーさん言ってたからお願いね」と伝えると、「そんなことわかってるよ」と不機嫌になることがあります。
「男ってプライドばっかりでちっさい人間やな」と思われることでしょう。
とはいえ、プライドを傷つけず感謝を伝えれば動いてくれるというのはシンプル(単純)ですし、時に父親の変化は膠着した状態を大きく変える力になります。
お父さんだってやり方がわからないだけで「大切な子どものために何かサポートしたい」という気持ちの方は多いですよ。
まとめ:一般的な夫へ協力を頼むときに気をつけること
- 何でも良いので小さな感謝から入る。
- 「お願い」や「頼る」といった「ワンダウンポジション」で伝える。
- 行動のハードルは下げておいてあげる(私も難しくてなかなかできないんだけど)。
- 結果まで教えてあげる(昨日子どもがお父さんが珍しく~~してくれたと言ってくれたよ)
普段から非協力的な夫にで「ワンダウン」なんて死んでもやりたくない!という方も多いかとは思いますが、「死んでもやりたくないこと」や「お子さんが見てびっくりすること」こそ変化に役にたつことは多いですよ。
3.夫が発達障害で私はカサンドラ症候群かもしれないと思う方へ
お母さんのカウンセリングしていると、常識の範囲では理解できないくらい旦那さんの理解がわるい場合があります。
話を詳しく聞いていくと旦那さんに発達障害(特にASD)の特性がありそうだなという場合があります。
ASDの方は物事に柔軟に対応するのが難しい場合が多く、不登校対応の協力を得るのが難しい場合もあるでしょう。
発達障害かどうかは別にして、どうにも悪循環が解けないときは改善しようとするのをやめ距離をとることも選択肢の1つです。
家族の状況によってケースバイケースですが、対応に困ったときは医療機関や教育支援センターなど、専門家に相談してみてください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
私の現在の不登校支援の結論は以下の記事に書きましたので、あわせて参考にしてみてください。
本記事で参考にした書籍は以下の本です。親御さんへの心強い言葉がたくさん書いてあり、おすすめの1冊です。