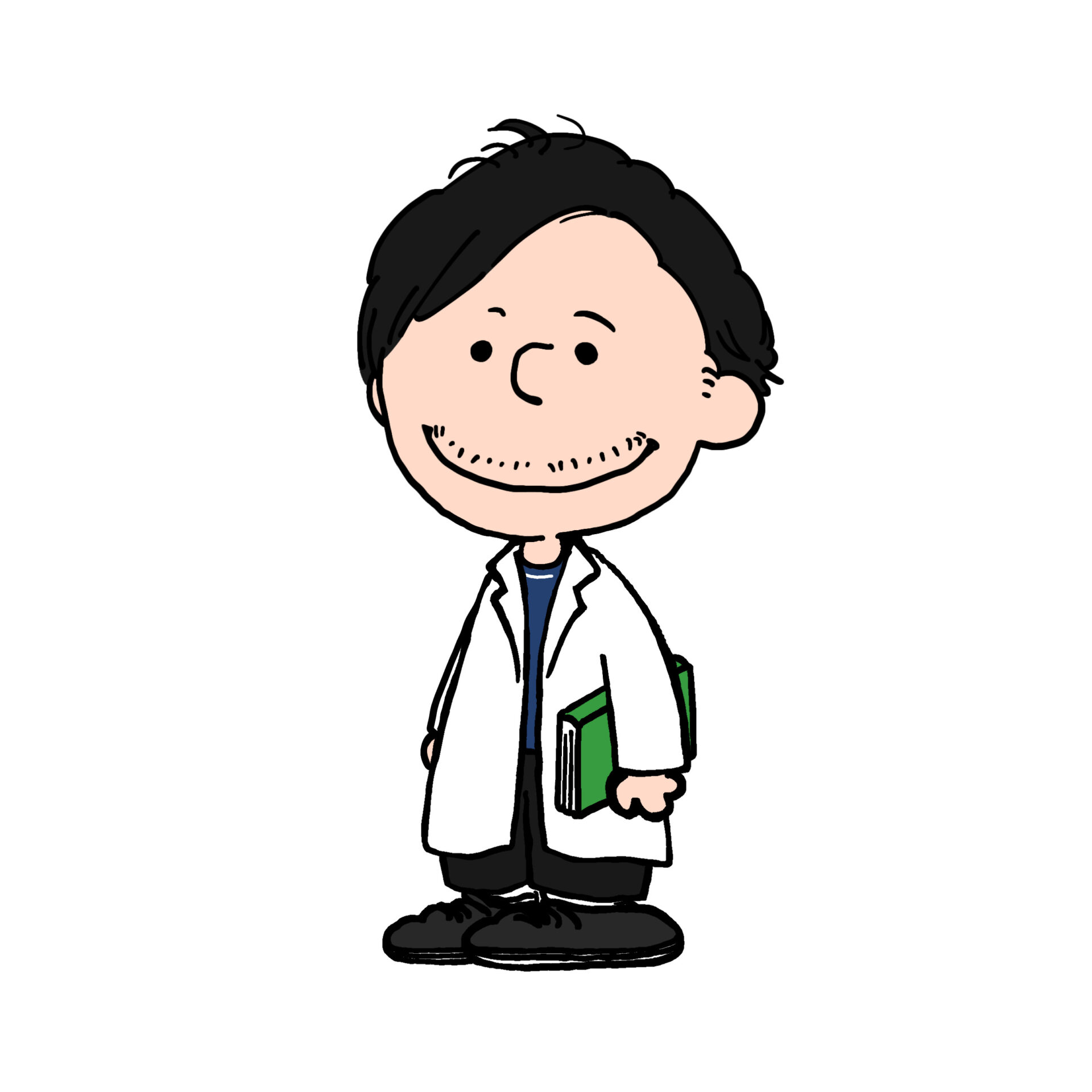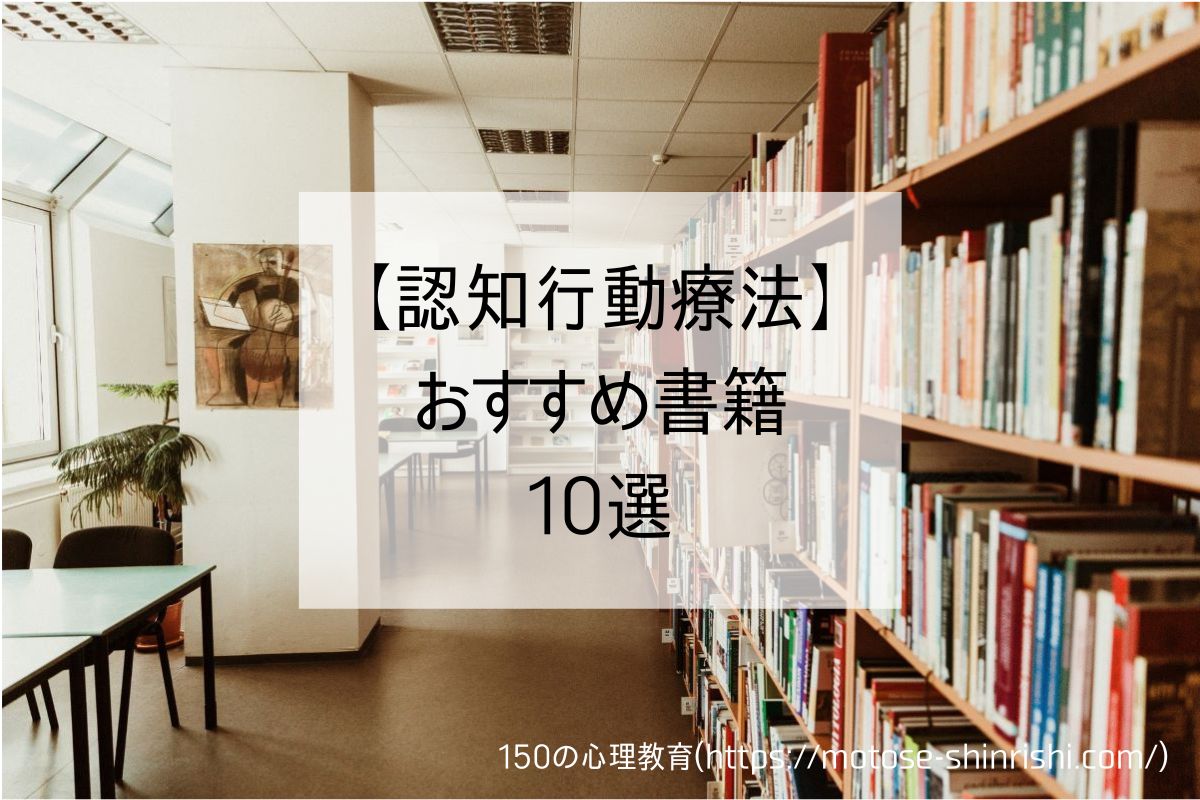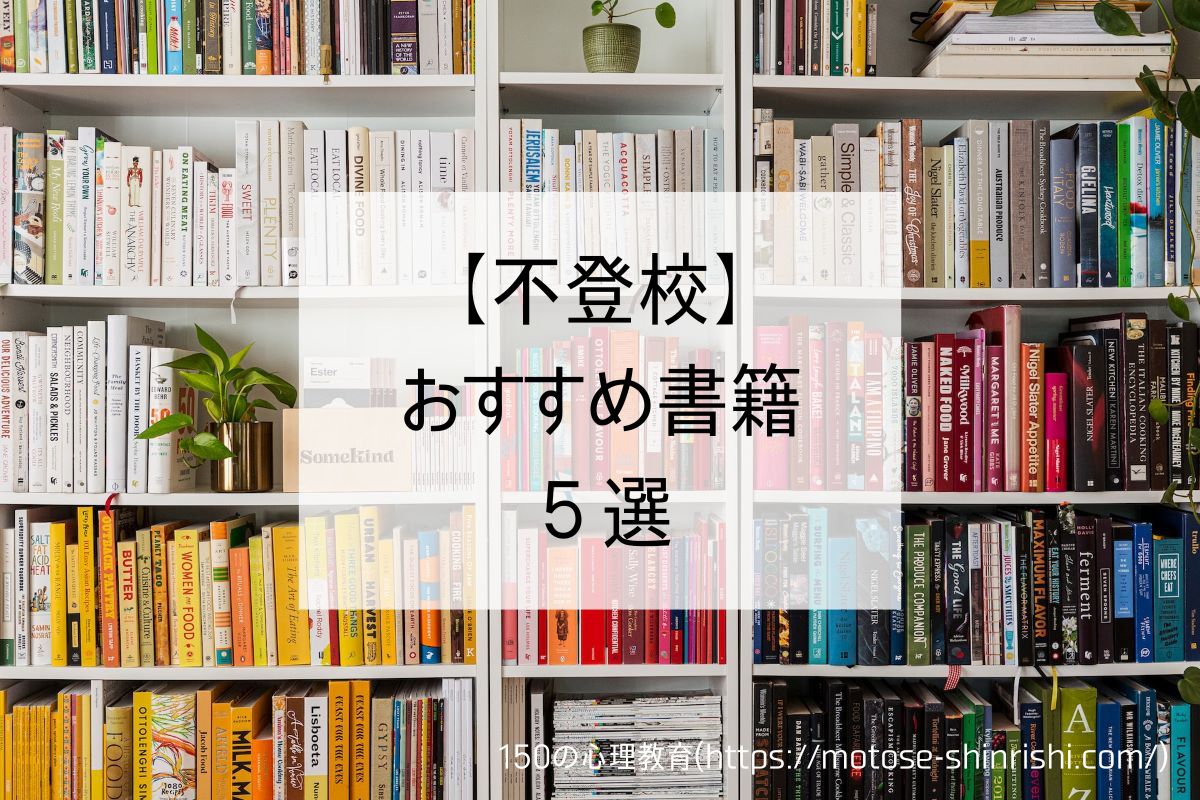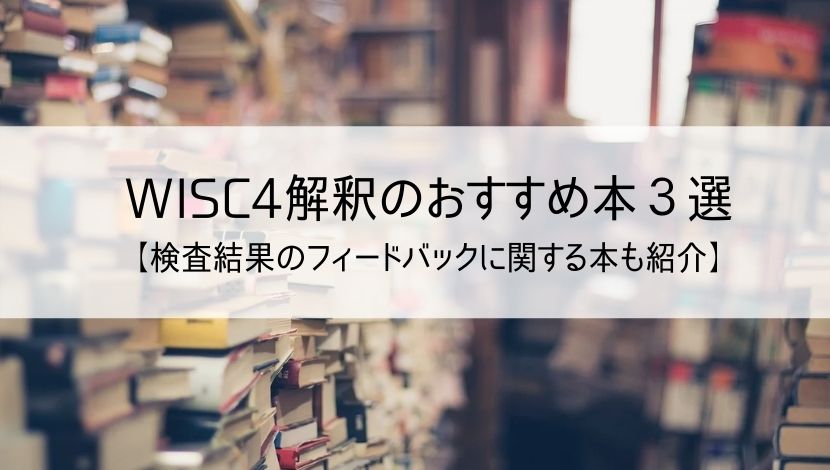こういった疑問にお答えします。
本記事の内容
- ASD(自閉症スペクトラム)の不登校対応【小学校から高校まで】
- ASDのお子さんの高校卒業後の選択肢とは?
- コミュ力よりも大切なものを理解できれば、不安にならなくて大丈夫です
私は児童精神科や学校で不登校のお子さん・親御さんのカウンセリングをしていたで臨床心理士です。
ASDのお子さんのカウンセリングをではどのように理解して進めればよいか悩んだ経験があります。
その経験をもとに得た知識で書いていきますので、参考にしてみてください。
前提として、ASDの確定診断かグレーゾーン診断を受け、かつすでに不登校になっているお子さんへの対応について書いています。
予防ではなく、事後対応について書いています。
ASD(自閉症スペクトラム)の不登校対応【小学校から高校まで】
私の考える、ASDの不登校対応で大切なポイントは以下5つです。
- まずは家で安心して好きなことができるようになる
- 親御さんが積極的にお子さんの趣味に関心をもつ
- 好きなことや強みを活かして仕事ができればそれに越したことはないが、それは結果としてそうなるだけであって、親が無理に仕事に結びつけようとはしない
- お子さんが進みやすい進学先や居場所を用意しておく
- 障害者手帳や就労移行支援などの福祉サービスを調べ、タイミングをみはからって提案する
不登校の原因にはいろいろな要因がまざっており、ASDだけでは説明できません。
ただし、対人関係やコミュニケーションの苦手さや独特のこだわりが学校生活、特に人間関係に影響するのは間違いあいません。
こだわりの強さがあり、一度「学校が嫌だ!」となると、その考え方を修正するのが難しいお子さんが多い印象です。
かといってASDお子さん自身は「学校なんてどうでもいい」「学校は行かなくてよい場所」とは思っていません。なんだかんだで、学校を意識していますし、意識しないように自分の好きな何かに打ち込んでみたりします。
ASDのお子さんは「他者からどう見られるのか」に無頓着な方が多いですが、中学生、高校生になると「他者視点でものごとを見られる」ようになってきます。
「自分は人と違うのか」と感じ、親の知らないところでひそかに傷ついていたりします。
そして、ASDのお子さんは自由に答えてよい系の会話が苦手なため、自分の気持ちを言葉にすることが苦手です。
「なんで学校に行けないの?」という抽象的な質問に答えることはとても難しいことでしょう。
このような理由から、学校に行けない理由を聞きだすことは得策ではありません。
そこは深追いせずに不登校の一般的な対応で言われている肯定的なことばがけを続け、必要に応じて適応指導教室や通信制高校など、本人が安心できる居場所を探してあげるとよいかと思います。
では次に、ASDのお子さんが高校卒業した後の選択肢について紹介します。
ASDのお子さんの高校卒業後の選択肢とは?

ここでは、進学先と就労に向けたサービスを4つ紹介いたします。
- 通信制の大学
- 専門学校
- 就労移行支援
- ハローワーク、発達障害支援センター
1.通信制の大学
勉強したいことはあるけど毎日の登校は難しい、そんな方は通信制大学が合っているかもしれません。
入学試験はほぼあってないようなもので、入学の難易度は低いです。
スクーリングがほとんどないのはメリットですが、「就職活動は自分でやらないといけないのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
全ての大学かはわかりませんが、就職支援が充実している通信制大学もありますので、興味のある方は資料で調べてみてください。
>>自分のペースで学べる通信制大学特集!まずはカンタン資料請求≪無料≫(外部サイト) ![]()
2.専門学校
専門学校は登校する必要はありますが専門知識を学ぶことができますし、資格を取って就職活動を優位に進められることがメリットです。
同じ趣味をもった学生と出会うことができるのもよい点ですね。
私は東京にあるIT系の専門学校の卒業生ですが、今思えば同じクラスにASDっぽいコミュニケーションが独特な方が何名かいました。
専門学校については高校の先生に聞いてみたり、資料を読んだりして調べるとよいでしょう。
3.就労移行支援
生活リズムは安定しており、ある程度の活動ができる体力や気力があるものの、働くためのスキルが十分に身についてない方には就労移行支援がよいかもしれません。
就労移行支援でできることを大雑把に言えば「働くための練習」です。
プログラムの内容は事業所によって異なりますが、概ね以下の流れをとります。
- 障害理解や健康管理などを行う基礎の段階
- 事業所内で作業をしながらマナーや報連相などの練習を行う就職準備の段階
- 実際の企業に見学に行ったり、実習に行ったりする実践的訓練の段階
- 就職活動
- 就職
就労移行支援事業は利用期間が2年と限られていますが、専門の就労支援スタッフが定期的な面談をしてくれるなど、手厚く支援してくれるところが特徴です。
利用するには事業所に見学や相談に行った後、自治体の障害福祉窓口に相談します。
就労移行支援事業所は様々ありますが、LITARICOワークスは大手であり、多くの都道府県にあるので、最初に相談する場所としてはよいと思います。
無料で相談することができますので、参考にしてみてください。
>>そのひとりの「働きたい」にこたえる。【LITALICOワークス】(外部リンク) ![]()
4.ハローワーク、発達障害支援センター
ハローワークには「障害者専門窓口」が設置されており、専門の相談員さんが対応してくれます。もし障害者手帳をもっていれば、ハローワークで障害者雇用の求人を見ることもできます。
ハローワークには「就職支援ナビゲーター」という就職支援の専門スタッフもおり、当事者のニーズに応じたさまざまな支援(職豪相談・紹介、履歴書の個別添削、求人開拓など)を行ってくれます。
発達障害支者支援センターは発達障害を持つ人への支援を総合的に行うことを目的とした専門機関であり、相談者の年齢は問いません。
役割としては①相談支援、②発達支援、③就労支援、④普及啓発・研修の4つがあり、仕事に関する悩みも相談することができます。
4については以下の書籍を参考にさせていただきました。
不登校のお子さんは自らこういった情報収集する意欲がわかなかったり、やり方を知らなかったりします。
来るべき高校卒業時に備え、親御さんが情報をもっておけるとよいでしょう。
最後に、ASDのお子さんの社会性、ようするにコミュ力よりも大切なものについて解説して終わりたいと思います。
コミュ力よりも大切なものを理解できれば、不安にならなくて大丈夫です
ASDのお子さんを見ていると、どうしてもコミュ力の低さに目がいきがちです。
しかし、将来的な職場適応を決めるのはコミュ力ではなく「本人がめげずにやり抜く力」です。
ストレス耐性、自己肯定感、レジリエンス、言い方はなんでも良いですが、多少の失敗があっても「もう無理」とならず、人に相談しながら次はこうしてみよう、できる工夫はないかなどと考えることができれば、生きる力に繋がります。
その気持ちを育てるのは日々の親御さんの肯定的なことばがけです。
具体的なほめ方は以下の記事を参考にしてみてください。
本記事は以上になります。他にも不登校関係の記事がありますので、よかったら参考にしてみてください。