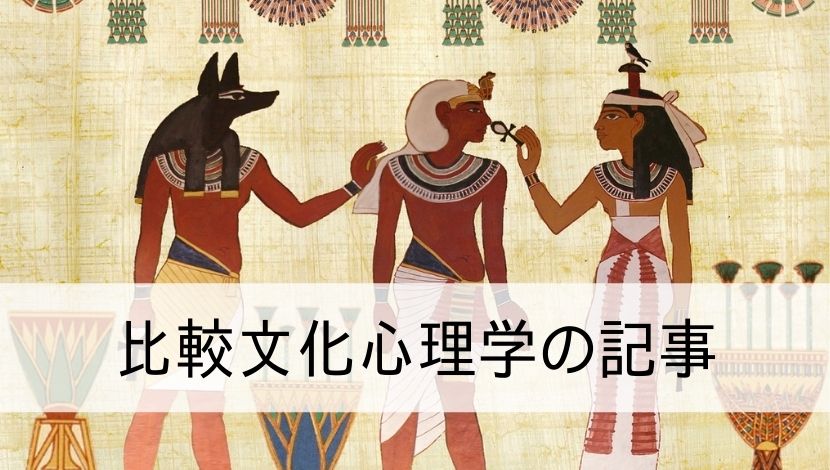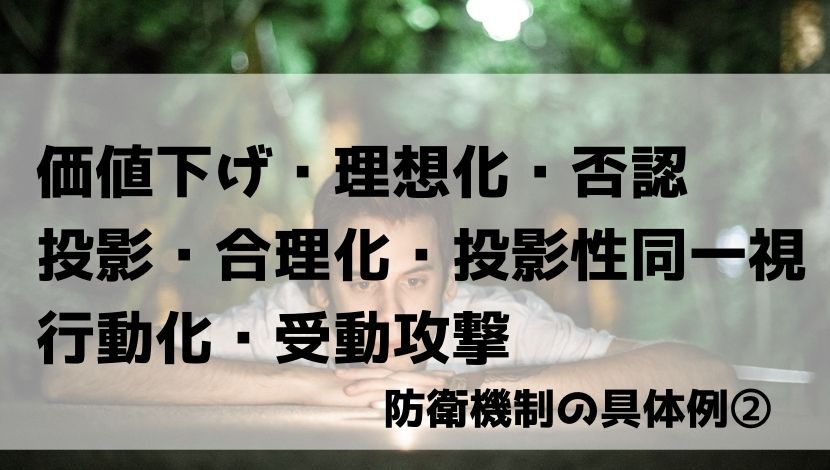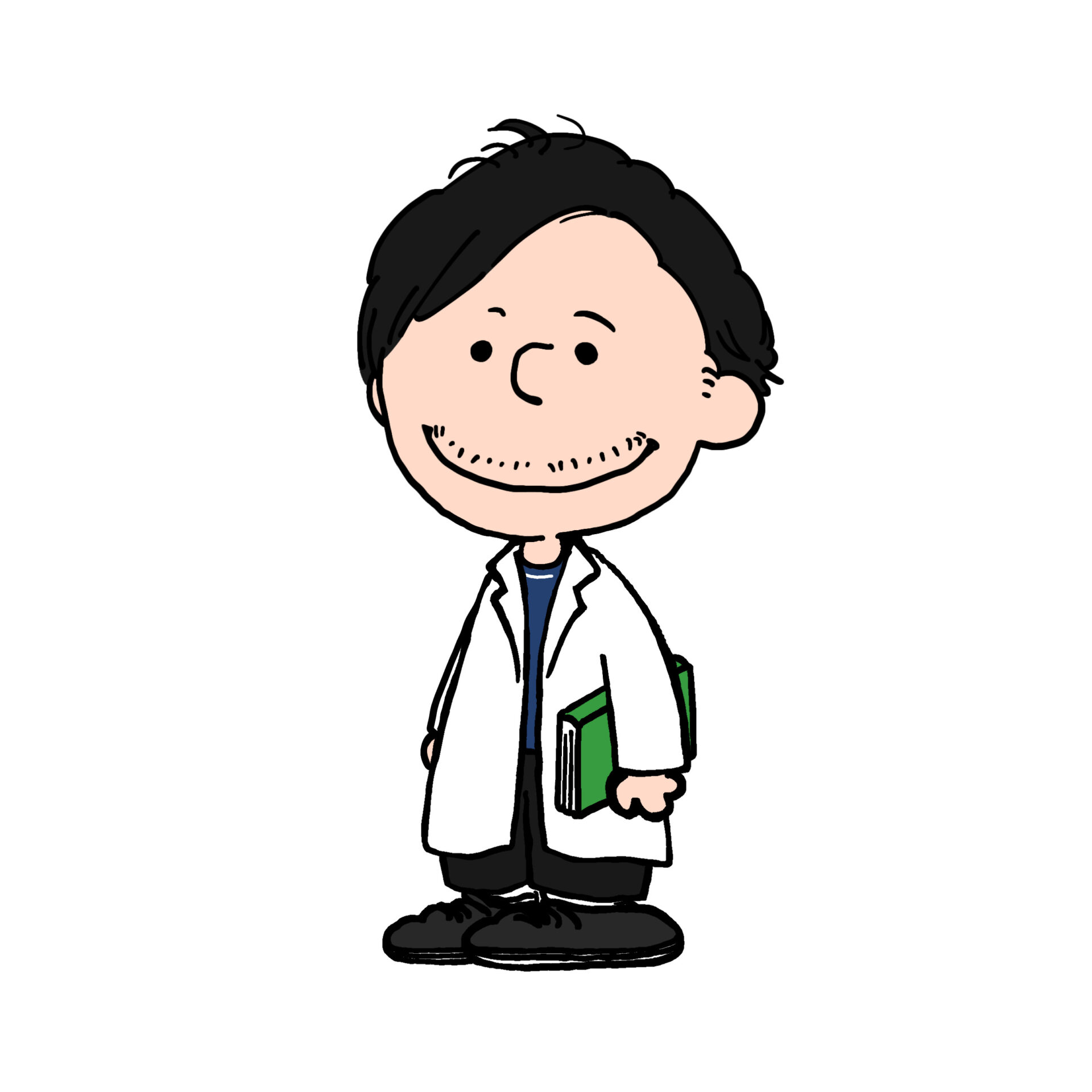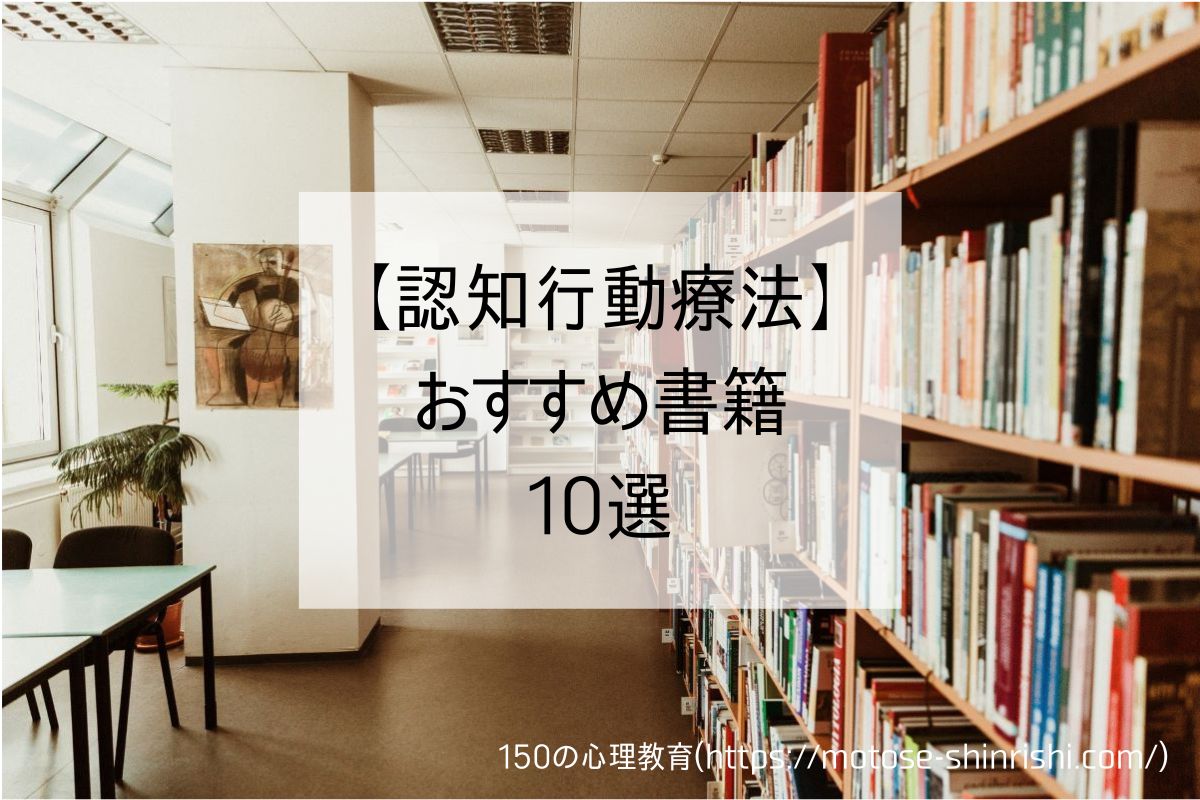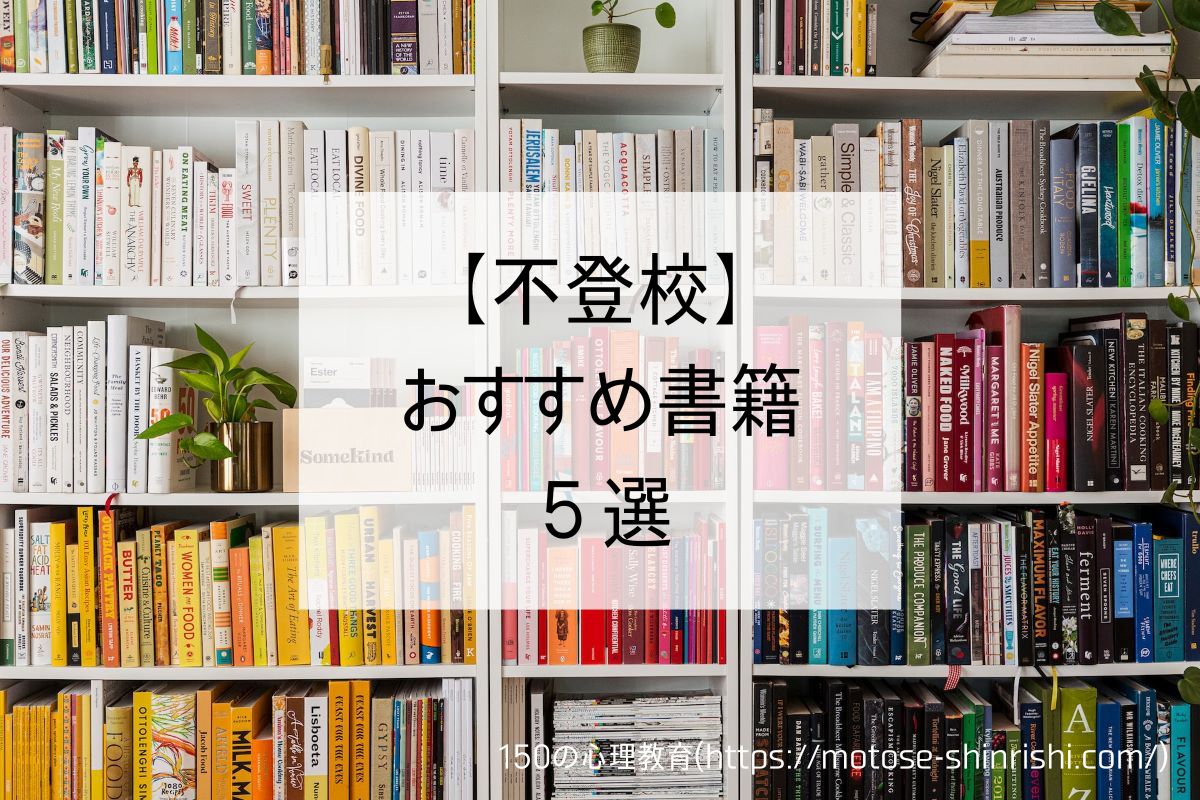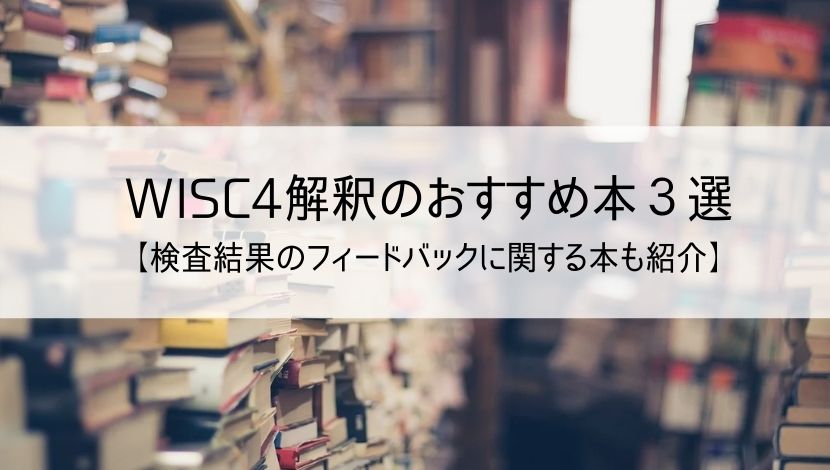こんにちは、モトセです。
本記事では自分と似た人を嫌いになる「同族嫌悪」になる理由と治す方法についてご紹介します。
カウンセリングを行う中でも、似た人を嫌いになってしまうというクライアントさんと時々お会いすることがあり、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
忙しい方に向けて、2分で読める程度に凝縮してまとめていますので、参考にしてみてください。
同族嫌悪の心理
最初に同族嫌悪の定義をご紹介します。
【同族嫌悪の意味・定義】
”同じ種類や系統のものを嫌悪すること。自分と同じ趣味・性質を持つ人に対して抱く嫌悪感”(Weblio)。
性格だけでなく、同じ趣味・指向をもった人を嫌いになることも含まれるようです。
結論から言えば同族嫌悪になる理由は以下の2つです。
- 自分の影(シャドウ)を相手に見出したから
- キャラ被りを避けたいから
1つずつ解説していきます。
理由1:自分の影(シャドウ)を相手に見出したから

影(シャドウ)とは、精神分析家のカール・ユングが提唱した概念であり、その人の生きてこられなかった側面のことをいいます。
以下のような種類があるといわれています。
- 認めたくないけど自分も持っている部分(普段隠している自分の嫌な側面)
- 自分が受け入れられない現実や価値観
- 自分が持っていないのを分かっていて、あこがれている部分
同属嫌悪がおきる理由の1つは、自分が持っている、普段隠している自分の嫌な側面(シャドウ)を相手に投影した結果です。
別の言い方をすると、同族嫌悪をする人は、自分自身のことが嫌いなのです。もちろん自分のすべてが嫌いなのではなく、一部かもしれません。
理由②:キャラかぶりを避けたいから
同族嫌悪が生じる理由の2つ目はキャラがかぶることを避けたいからです。
この理由は特に思春期によく見られると言われています。集団の中に同じような人間が2人いると、ユニークさという価値がなくなり、自分のアイデンティティがゆらぎます。アイデンティティ達成がテーマである時期においては、その状態がたまらなく不快なのです。
これが2つめの理由です。
同族嫌悪を治す方法
影には「克服すべき課題」と「受け入れるべき生き方や価値観」という2面性があります。
よって、同族嫌悪を治す方法は以下だと言えます
- 自分の嫌な部分を変えて克服する
- そういう自分も自分だよなと受け入れる
自分の嫌な面であれ、自分の一部です。否定し続ければ生きていて疲れます。今まで抑圧されたり否定されてきた自分の一部を克服したり、受け入れたりすることは、心の健康を保つために大切なことだといえるでしょう。
この人のことなんか嫌いだなーと感じたら、「自分も同じところはない?」「それを受け入れることはできている?」と脳内会議をしてみることで、なにか気づきを得られるかもしれません。
ご覧いただきありがとうございました。
他にも心理学コラムを書いております。気軽によんでみてください。

発達心理学
2022/4/16
心理学的な「アイデンティティ」の意味【エリクソンの漸性発達理論】
「好きな服は何ですか?好きな本は?好きな食べ物は何?そう、そんな物差しを持ち合わせてる僕は凡人だ」 これはサカナクションというバンドの「アイデンティティ」という曲の一部です。自分が何者かを見つめる過程が生々しいくらいに研ぎ澄まされている感じがします。 人は特に青年期に自分が自分であるための”らしさ”を求めます。 今回はそんな自分らしさに関する概念【アイデンティティ(identity)】を紹介していきたいと思います。 アイデンティティとはなにか アイデンティティとエリクソンの漸性発達理論 アイデンティティと ...
ReadMore

文化心理学
2022/3/6
価値観の違いっていうけど価値観ってどんな意味? 比較文化心理学による説明
カップルが別れる原因としてよく言われるのが“価値観の違い”というやつですが、価値観って何か説明できますか? 今日はそんな漠然とした価値観ということを比較文化心理学に基づいて解説していきます。 ■価値観とは何なのか ちなみに価値観という言葉を辞書で引くと以下のように書いてあります。 “いかなる物事に価値を認めるかという個人個人の評価的判断” ※出典:Weblio(大辞林) 意外とよくわからないですね。 比較文化心理学で価値観を説明する際に使われるのが、Hofstedの文化概念のたまねぎ型モデルというやつです ...
ReadMore

精神分析
2022/4/16
【具体例】価値下げ・理想化・否認・投影・合理化・投影性同一視・行動化・受動攻撃|自我の防衛機制2
精神疾患の診断マニュアルであ「DSM-IV」の付録には、様々な防衛機制が7つの「水準」に分けて掲載されています。※今後の研究のために提案された軸として「付録」として記載されています。 この記事では7つの水準のうち「イメージの軽度歪曲の水準」「否定の水準」「重度のイメージ歪曲の水準」「行為的水準」「防衛制御不能水準」の中から「価値の引き下げ」「理想化」「否認」「投影」「合理化」「投影性同一視」「行動化」「受動攻撃」を紹介します。 前回記事は以下です。 【具体例】昇華・ユーモア・抑制・置き換え・ ...
ReadMore

性格心理学
2022/4/6
【なぜ?】2分でわかる同族嫌悪の心理【その意味と治す方法】
こんにちは、モトセです。本記事では自分と似た人を嫌いになる「同族嫌悪」になる理由と治す方法についてご紹介します。 カウンセリングを行う中でも、似た人を嫌いになってしまうというクライアントさんと時々お会いすることがあり、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 忙しい方に向けて、2分で読める程度に凝縮してまとめていますので、参考にしてみてください。 同族嫌悪の心理 最初に同族嫌悪の定義をご紹介します。 【同族嫌悪の意味・定義】”同じ種類や系統のものを嫌悪すること。自分と同じ趣味・性質を持つ人に対して抱く嫌悪 ...
ReadMore