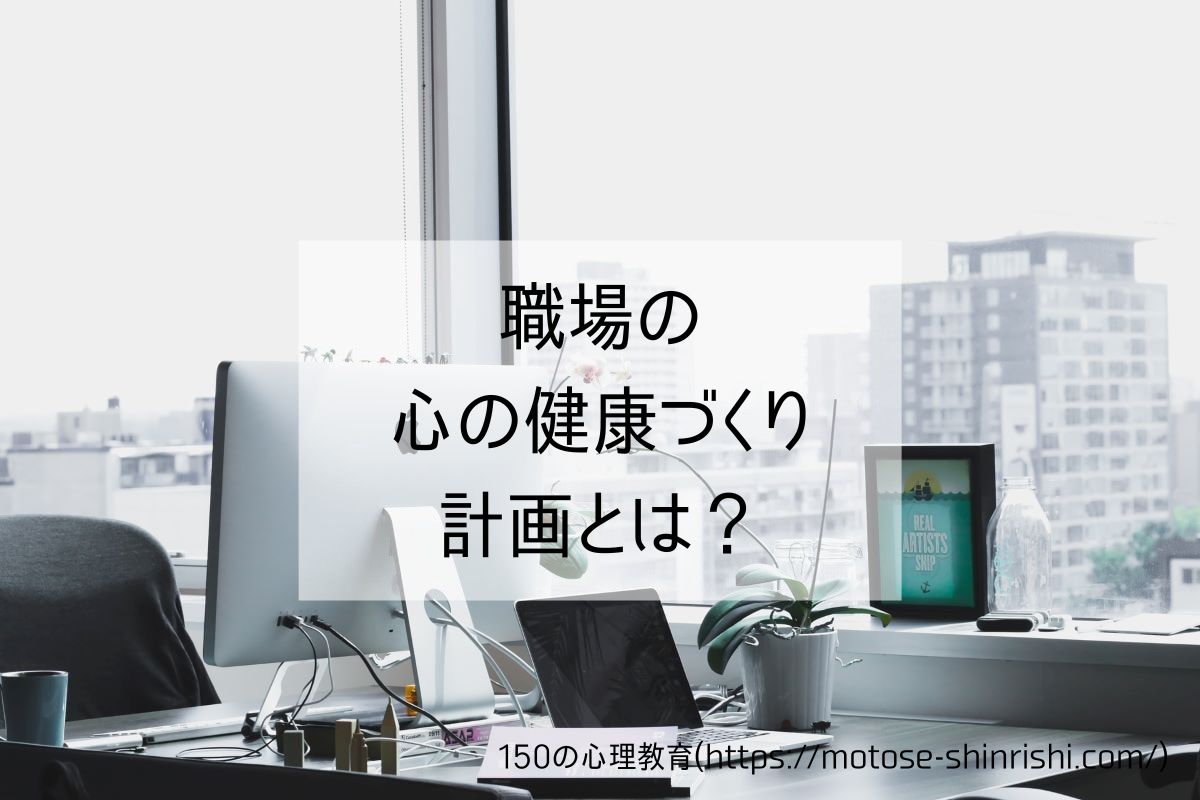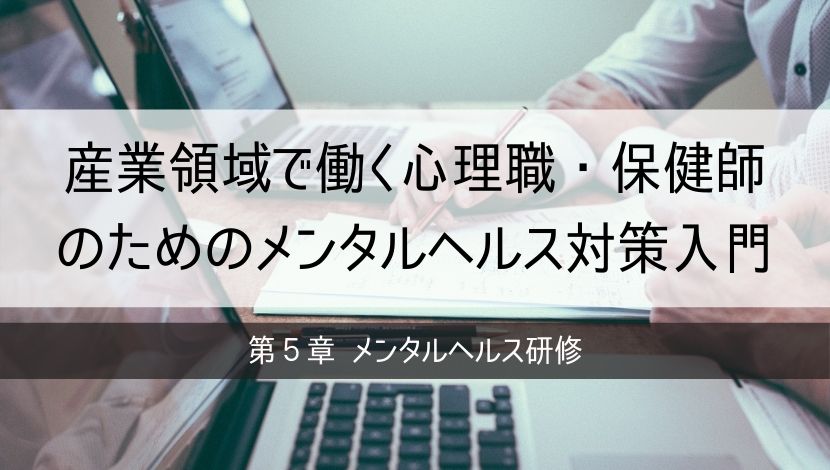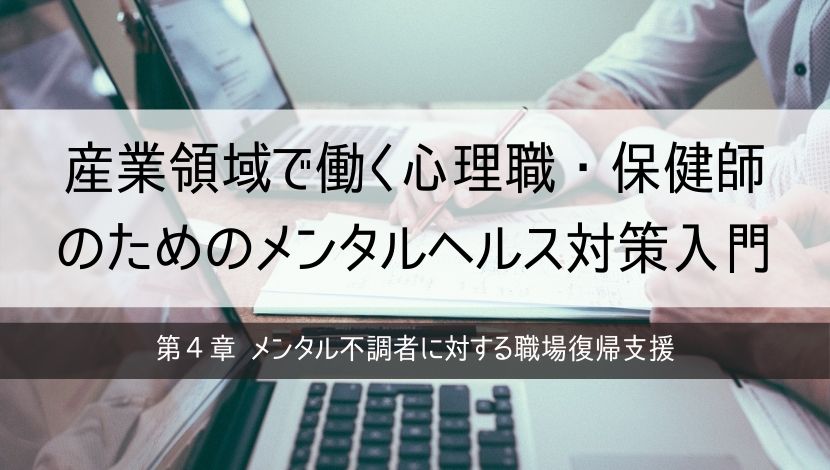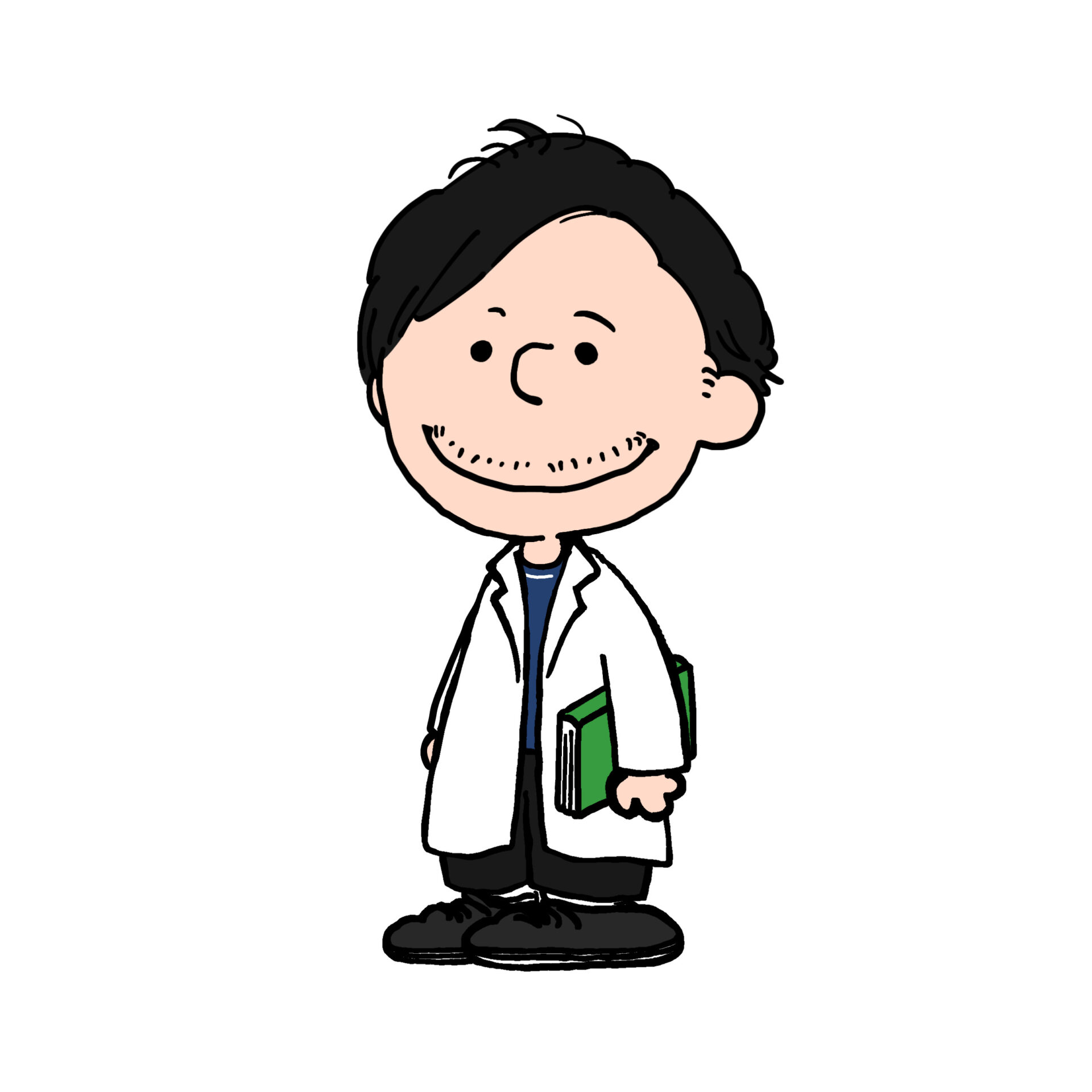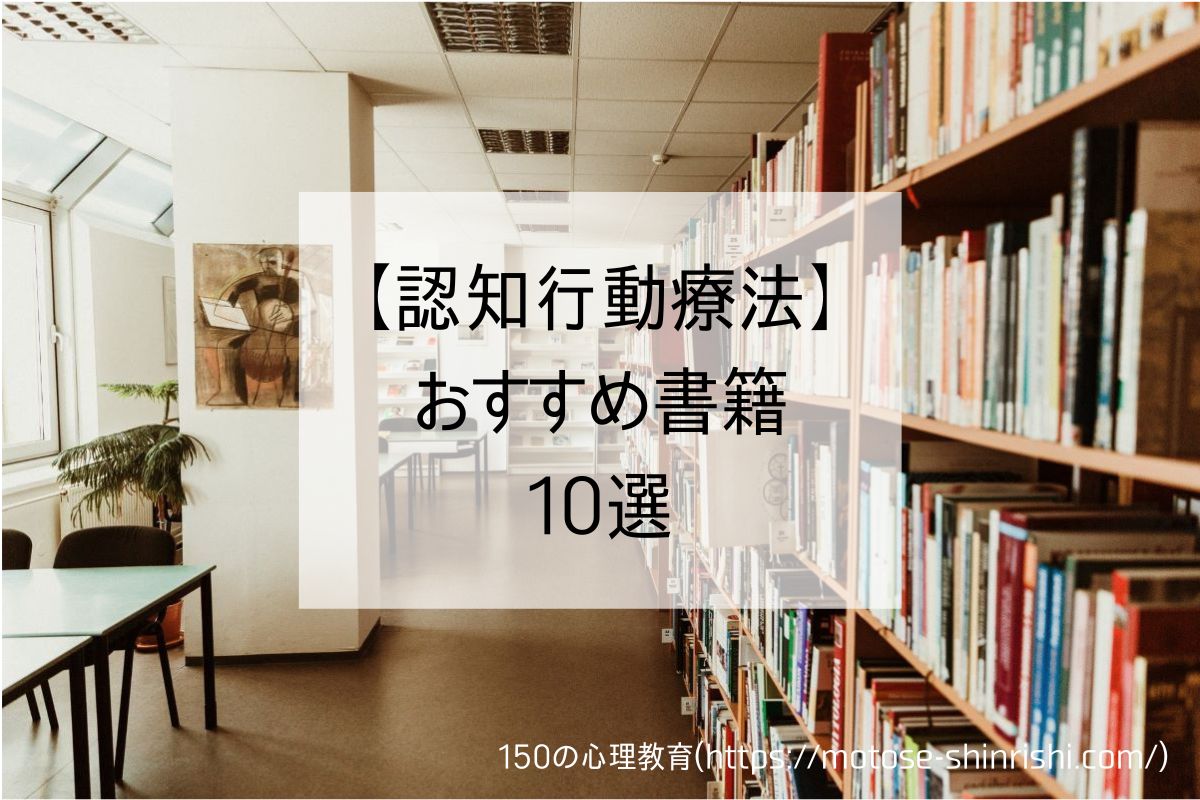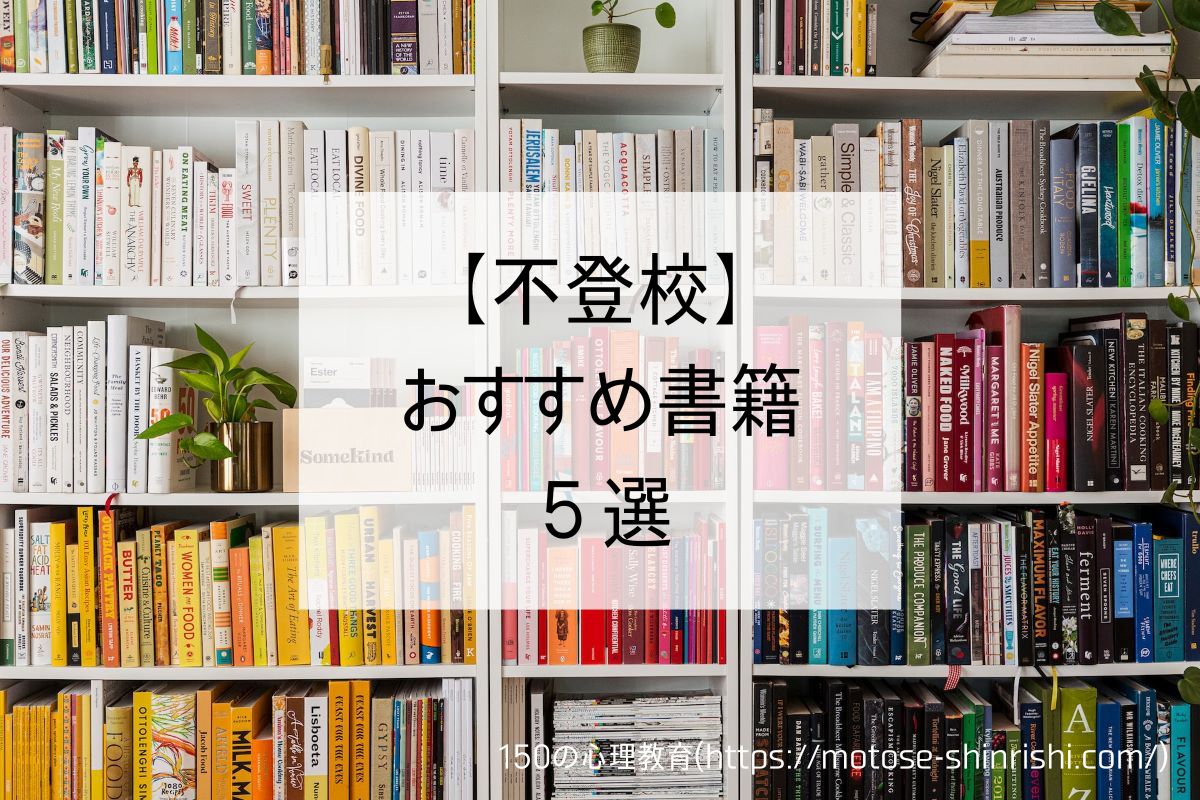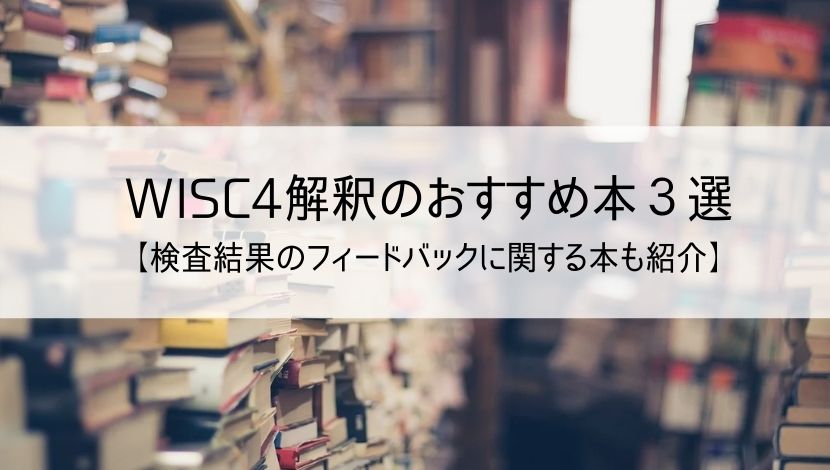こういった疑問にお答えします。
本記事の内容
- 職場の心の健康づくり計画とは?
- 職場の心の健康づくり計画のひな形(サンプル)3選
- 職場の心の健康づくり計画の内容を臨床心理士が解説
記事の信頼性
私は以前、組織内で心理的支援をしていた臨床心理士です。職員のメンタルヘルスケアや年間計画の作成、メンタルヘルス研修の講師を行っていました。
職場のメンタルヘルスを向上させる。言葉で言うのは簡単ですが、どうやればいいのでしょうか。目標達成には計画が重要であり、それが心の健康づくり計画です。
一言で言えば、職員のメンタルヘルスを保持増進するために「いつまでに」「こんな取り組みをするので」「皆ちゃんとやってください」と周知する資料です。

という方のためにネットで閲覧できるひな形(サンプル)や、作成する際に参考になるWordファイルへのリンクもあります。
コーヒーでも飲みつつゆっくりご覧ください。
職場の心の健康づくり計画とは?

職場の心の健康づくり計画とは、職員のメンタルヘルス(精神的健康)の保持・増進にあたって必要とされる取り組みを記した計画書です。
策定する理由は、正直ベースでいえば「助成金」という会社もあれば、優良企業の印象をつけるため、本当に職員の健康のためという会社もあると思います。
ちなみに作成は義務ではなく、努力義務のようです(日本の人事部を参考)。
なお、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(以下「指針」と記載)には次のように書かれています。
事業者は、自らがストレスチェック制度を含めた事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に 推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」 やストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定する必要があります。
また、その実施に当たってはストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタル ヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う 「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が円滑に 行われるようにする必要がある。
これらの取組みにおいては教育研修・情報提供を行い、「4 つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のため の支援等が円滑に行われるようにする必要があります。
こうやって必要性を訴えられても実物を見ないと全くピンときませんよね。私はピンときませんでした。
さきにリンクを紹介しますので、イメージをつかむ参考にしてみてください。
職場の心の健康づくり計画のひな形(サンプル)Wordファイルも

職場の心の健康づくり計画のひな形を3つ紹介します。
※リンク最終確認(2022年6月13日)
なお、指針には「心の健康づくり計画」に盛り込む内容として以下が挙げられています。
- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
- 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
- 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
- メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
- 労働者の健康情報の保護に関すること
- 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
上記ひな形(サンプル)を見たところ、これらの項目通りに記載する必要はなく、これらの内容が含まれていることが重要のようですね。
では次の章で、これら6項目の具体的な内容について補足していきます。実際に策定する際の参考にしてみてください。
職場の心の健康づくり計画の内容を臨床心理士が解説

以下の項目について、それぞれ補足していきます。
- 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
- 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
- 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
- メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
- 労働者の健康情報の保護に関すること
- 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
1.事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
一言で言えば、心の健康づくりの活動方針のことです。
メンタルヘルス対策に本気で取り組みますよ、というメッセージを伝えるために重要です。
具体的には、位置づけや目標がこの部分にあたります。
メンタルヘルスのみならず、ハラスメントについても積極的に推進する旨を表明することが重要です。
2.事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
一言で言えば、誰が何をするのかを記すことです。
ネットのサンプルを調べてよく出てくるのが、以下のような文言です。
従業員、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ、人事労務部門及び衛生委員会の役割を以下のとおりとする。
「心理職」や「保健師」は「事業場内産業保健スタッフ」に入ります。私の経験的な感覚ですが、メンタルヘルス対策に関係する人を以下に例示します。
管理監督者
「課長職以上」を管理監督者と呼ぶことが多いようです。
●●課の管理監督者は●●課長であり、その課でメンタル不調者が発生した場合、連絡窓口になったり、通院同行したりする人になります。
健康管理者
メンタルヘルス対策を含む、職員の心身の健康管理をする立場の人です。人事か福利厚生担当部署の課長さんが多い印象です。
事業場内メンタルヘルス推進担当者/事業場内産業保健スタッフ
心理職はここに該当します。資格的には臨床心理士、公認心理師、産業カウンセラー、産業保健師、衛生管理者、看護師等でしょうか。
人事労務担当者
人事担当部門の長のことで、配置換え(異動)や採用等、人事の采配をする人です。人事課の課長だと思って良いでしょう。
メンタルヘルス問題において個人や職場(課・チーム)の対応でどうにもできない場合、人事異動をするしかない場面が出てくるので、メンタルヘルス対策を行う上で、連携を密にとる必要がある人物となります。
産業医
言わずもがなの非常に強力なメンバーです。常時労働者数50人以上の事業場では産業医選任の義務があります。概ね以下の役割を担います。
- 心の健康づくり計画の企画・立案及び評価への協力
- 従業員、管理監督者からの相談への対応と保健指導
- 職場環境等の評価と改善によるストレスの軽減
- 従業員、管理監督者等に対する情報提供及び教育研修
- 外部医療機関等との連絡
- 就業上の配慮についての意見
産業医が常駐している企業は稀で、週に1回または月に1回来社して、上記のことを行うことが多いようです。
3.事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
実際にどんな対策をしていくかという内容の部分であり、非常に重要です。サンプルには以下の事項が記載されています。
(1) 職場環境等の把握と改善
ア 管理監督者による職場環境等の把握と改善
イ 事業場内産業保健スタッフによる職場環境等の把握と改善
(2) ストレスチェックの実施
(3) 心の健康づくりに関する教育研修・情報提供
(4) 事業場外資源を活用した心の健康に関する相談の実施
メンタルヘルス研修に関しては別の記事で解説しておりますので併せてご覧ください。
4.メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
契約している外部の精神科クリニックやEAP、無料相談サービスに相談できること等を明記するようです。
また、利用するための方法、連絡先、金額、利用したことで職員に不利益が生じないことも盛り込むといいでしょう。
5.労働者の健康情報の保護に関すること
言わずもがなですが「守秘義務は守りましょう」ということです。
また、情報ごとに閲覧できる職員を表にして明示する場合もあるようです。
6.心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
「目標設定」と「評価」は非常に重要なことです。
計画サンプルをいくつか見ているとわかりますが、
- 「メンタルヘルス研修の参加率を90%にする」
- 「管理職に傾聴スキルを身につけさせる」
- 「早めに医療機関にリファーする」
といった無難な目標に落ち着くことが多いようです。
そこからわかるのは「まずは当たり前のことを当たり前にできる組織にする」ことが大切ということです。それ達成できた後に、より高度な目標を設定すればいいと思います。
ただし、注意も必要です。
例えば、研修に90%参加したからといって、参加者が全員寝ていたらどうでしょうか? その効果はほぼ無いわけです。このような目標は、「研修を受けさせる」という体面的な目標を達成することはできていますが、「メンタル不調の防止に効果があったのかなかったのか」を判定するには不十分です。
そのため、数値で把握可能な目標設定も重要です。
例えば、
- 「ストレスチェックで把握する職場環境のリスクを前年度マイナス●点にする」
- 「良好な職場にするために肯定的なコミュニケーションを増やす」
- 「心理職が年度末にアンケート調査を実施し、今年度の計画の達成状況を5段階で評価してもらう」
等などです。
これは関係者間で相談して決めると良いでしょう。
本記事のまとめ
- 職場の心の健康づくり計画とは?
- 職場の心の健康づくり計画のひな形(サンプル)3選
- 職場の心の健康づくり計画の内容を臨床心理士が解説
他にも産業メンタルヘルスの記事を用意していますのでぜひご覧ください。