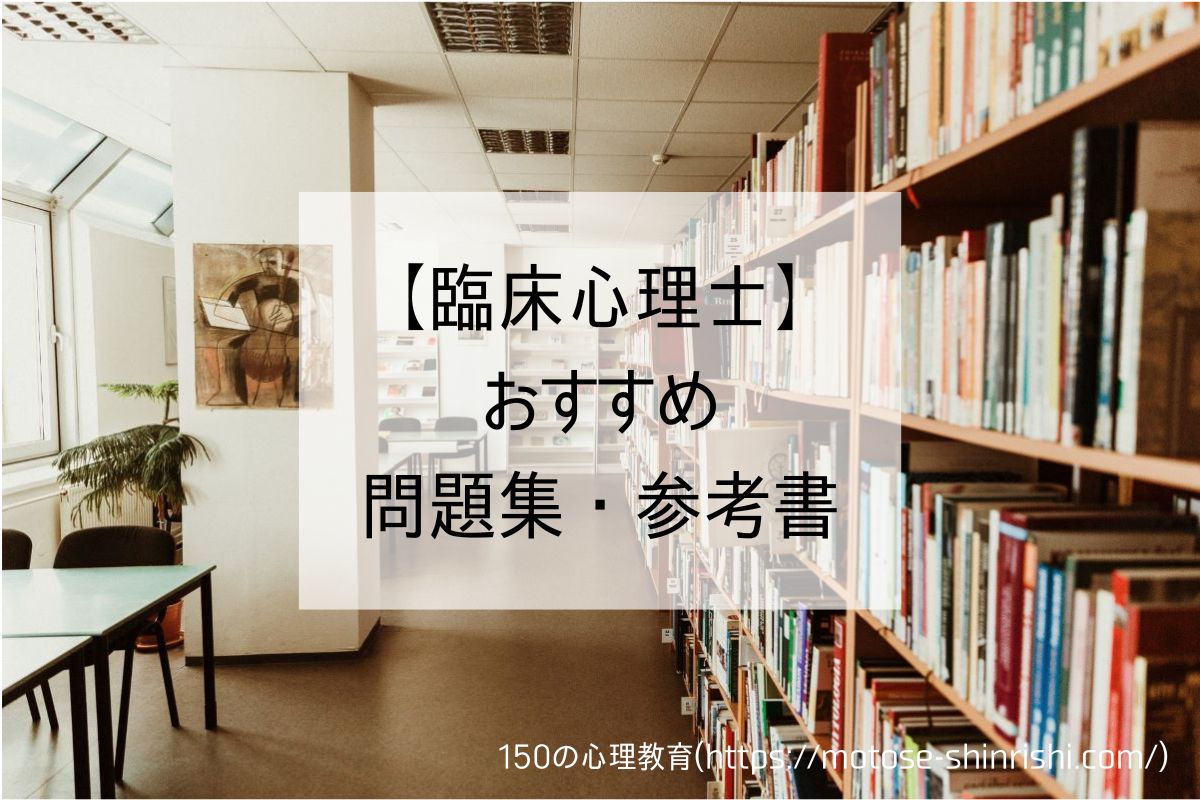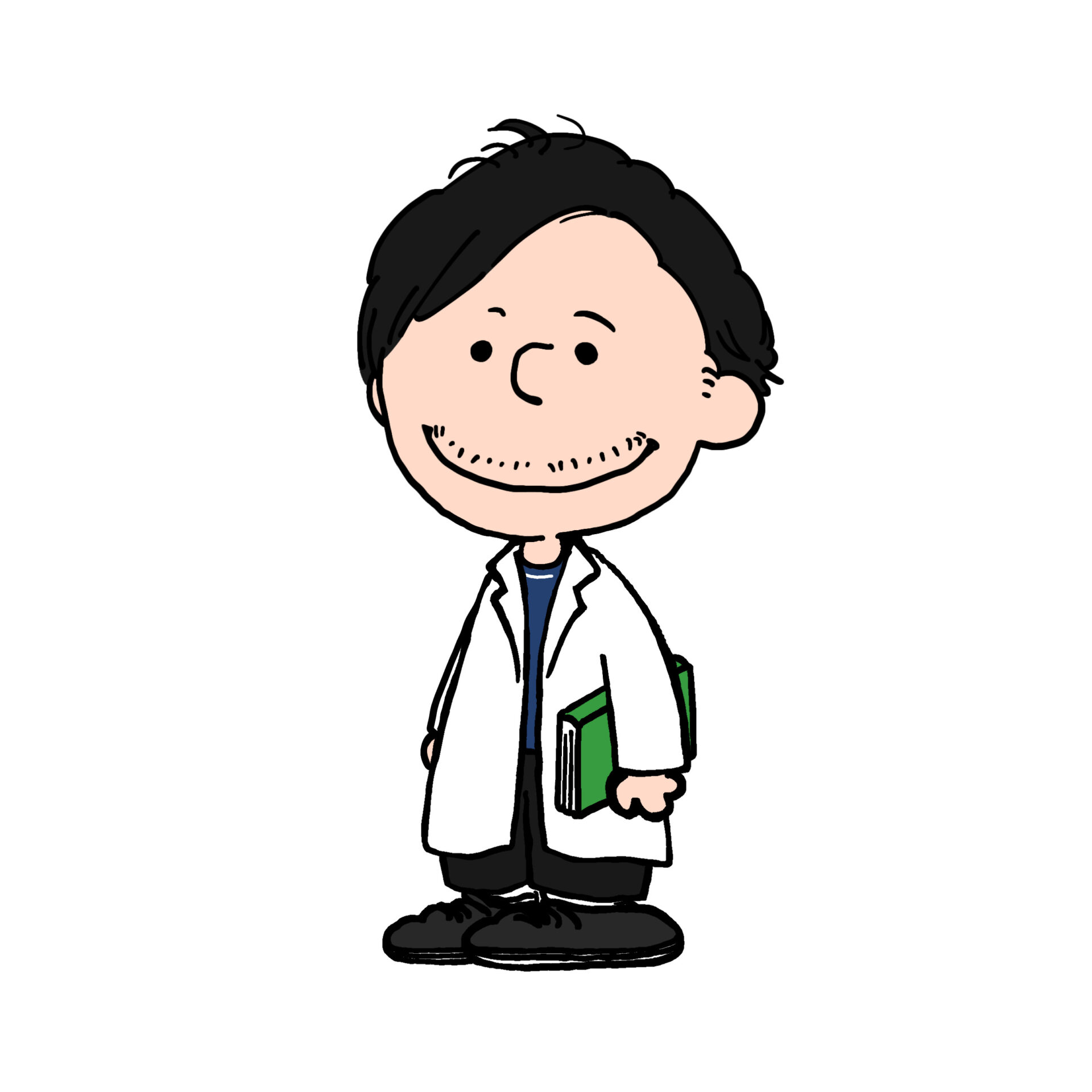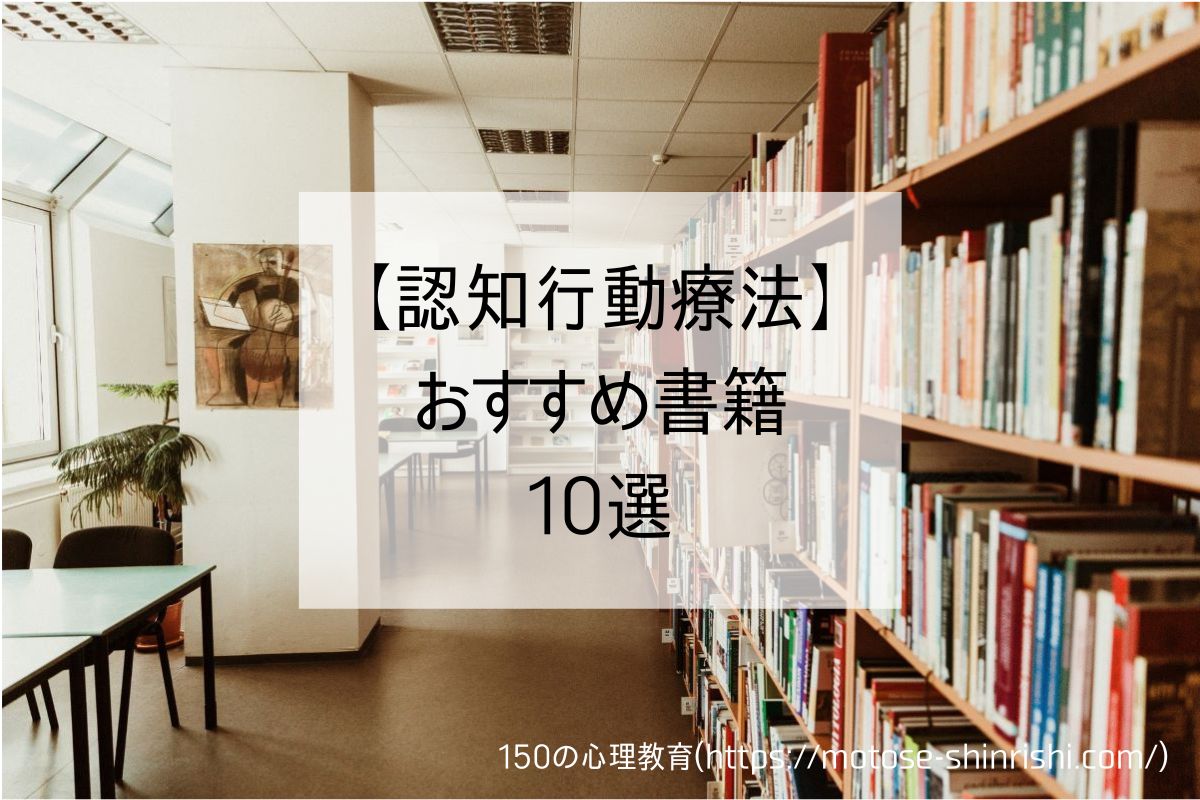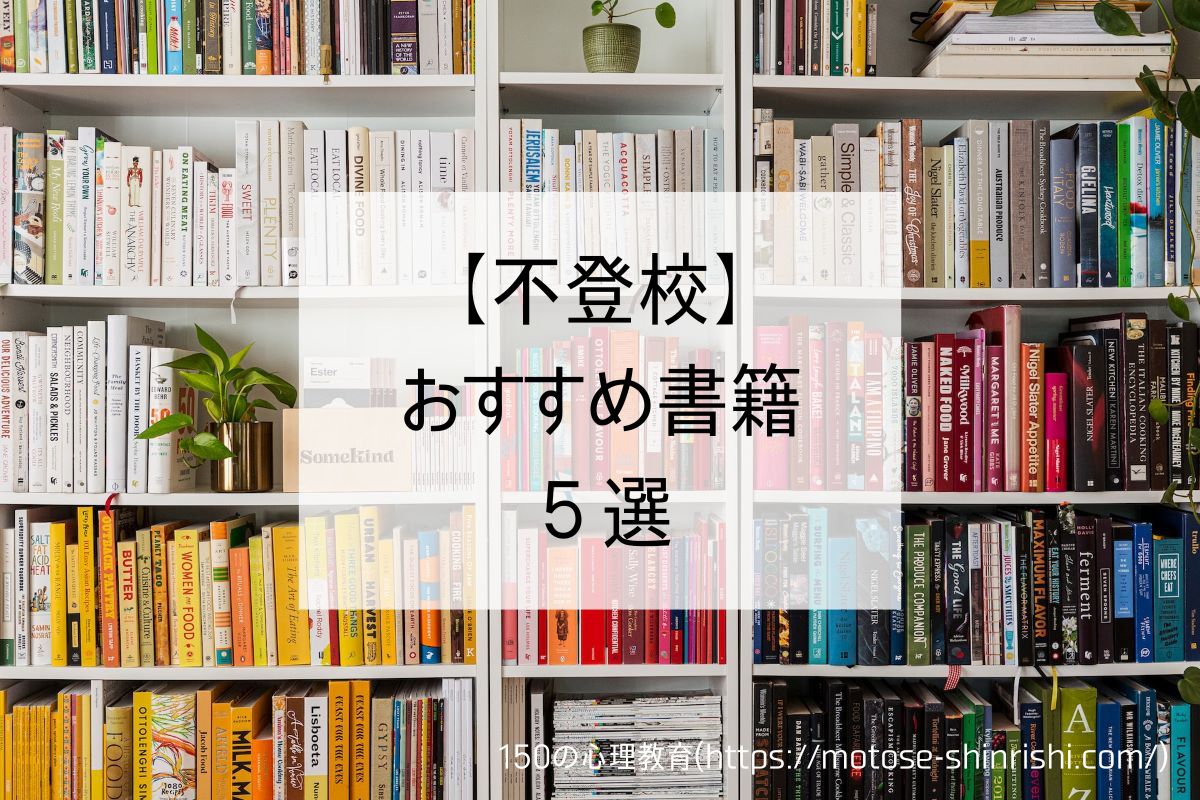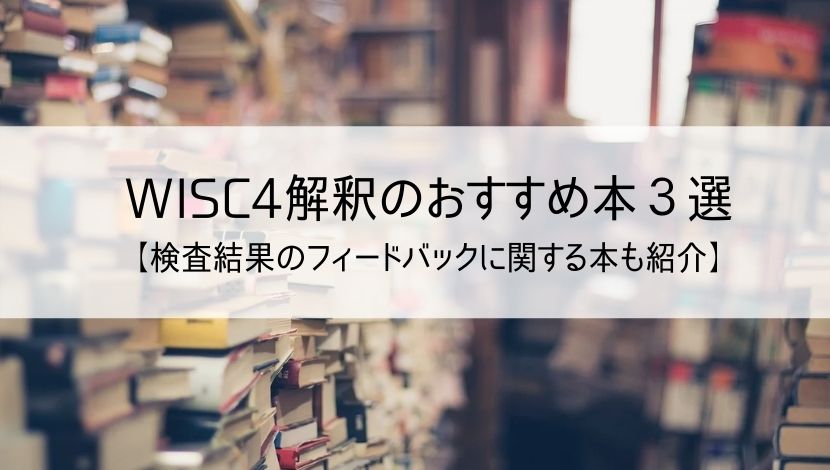こういった疑問にお答えします。
参考書は金額も高いですし、できればハズレを選びたくないですよね。
本記事では私自身や合格者仲間が使っていた鉄板のテキストを紹介するので参考にしてみてください。
以下に私が100%の自信をもっておすすめする「テキスト」(参考書)と「問題集」を掲載しています。
一次試験の午前(筆記)を中心にしていますが、午後(論述)や二次試験に使える鉄板本もあります。
公認心理師の対策本で臨床心理士の対策をカバーできるかですが、答えはNoです。
臨床心理士試験では心理療法や心理検査、面接などについて、公認心理師より細かいところを問われるため、臨床心理士試験用のテキスト(参考書)と問題集を買うことを強くお勧めします。
記事の途中で臨床力が驚くほど向上する「見立て」に関する良書も紹介していますので参考にしてみてください。
では、書籍を紹介していきます。
新・臨床心理士になるために
通称「赤本」でおなじみの「新・臨床心理士になるために」です。
なお、毎年7月に当年度版が出ています。
受験する人は何も考えずに買ってください。
試験の概要や倫理規定などが書いてあり、非常に重要です。
また、前年度の試験問題が約40問記載されているため過去問の要素も入っています(とても重要)。
臨床心理士資格試験問題集 1~5
通称「青本」でおなじみの過去問集です。
それぞれの年度で100問中の約40問が掲載されています。
なお、公認心理師のように全問が掲載されている書籍はありません。
私はその時点で出ているものは全て買いましたし、同期の多くの人が買っていました。
代々継承されていく研究室があるというのも聞いたことがあります。
私は最初に「最近のものだけあればよくないか?」と思っていたのですが、結論から言うと全て買った方がいいです。
1(平成3年~平成18年)の分量が一番多いですし、全て解いてみると意外と似たような問題を使いまわしてるんだな、ということがわかるからです。
注意点としては、過去の問題は過去の法律に基づいて作られていることです。
少年法などは変わっているので過去の問題の解説を鵜呑みにしてはいけません。
法律系の問題は最新の参考書を読んで学習しましょう。
一発合格! 臨床心理士対策テキスト&予想問題集
個人的にオレンジ本と呼んでいたテキストです。
参考書ではベストだと思います。
内容も分かりやすく書いてありますし、模擬試験100問が2回分ついているのが高評価です。
ただし2020年に出版されており結構前になってきたなと思います。
内容的には充実していますが最新の用語はカバーできていないことが予想されるため、次の書籍もおすすめです。
心理系大学院入試&公認心理師・臨床心理士試験のための心理学標準テキスト '25~'26年版
IPSA心理学大学院予備校のテキストは出版年がオレンジ本より新しく、公認心理師のテキストも兼ねているのが特徴です。
公認心理師の予想模擬試験がついているので二度おいしい感はあります。
オレンジ本に加えてこの本で演習することで徹底的に対策できると思います。
未だに新しい本を出し続けるというのはIPSA恐るべしです。
心理学キーワード&キーパーソン事典
大学院入試でお世話になった人も多いかもしれない頻出キーワード&キーパーソン辞典は臨床心理士対策でも使えます。
この単語何だっけ?という時にさっと引けるのがいいです。
何より小さくて持ち運びやすいのが良いです。
会場で見かけた本の前に
試験会場で試験前に一番多く見かけた本の紹介の前に、臨床心理士試験を受験される方の多くは現場に出て日が浅く「臨床力」自体に自信が持てない方が多いかと思います。
そんな方に心からおすすめの本が竹内先生の「100のワークで学ぶ カウンセリングの見立てと方針」です。
この本で読んでから実務をこなすのと、読まないで実務をこなすのでは1年後の臨床力に天と地ほどの差が出ます。
試験会場で試験前に一番多く見かけた本
私の受験した年の話にはなりますが「臨床心理士試験徹底対策テキスト&予想問題集」(上記の「一発合格! 臨床心理士対策テキスト&予想問題集」の古いバージョン)についている模擬試験の緑の冊子が会場内で目立ちました。
みんな同じ本で勉強しているんだなと安心した瞬間でした。
合格をお祈りしています!
(番外編)公認心理師試験 おすすめテキスト・問題集
公認心理師試験 おすすめテキスト・問題集は以下のページで紹介しています。