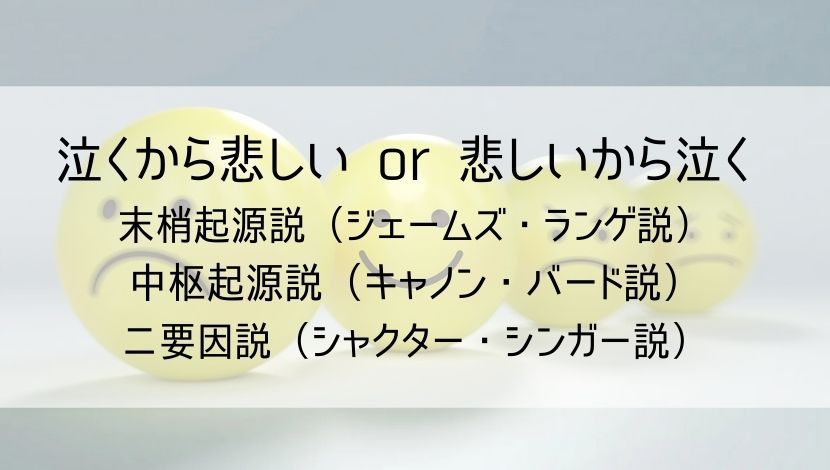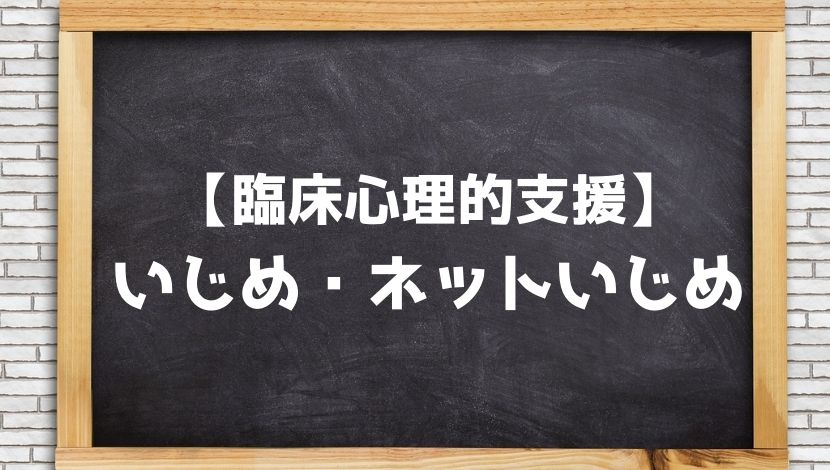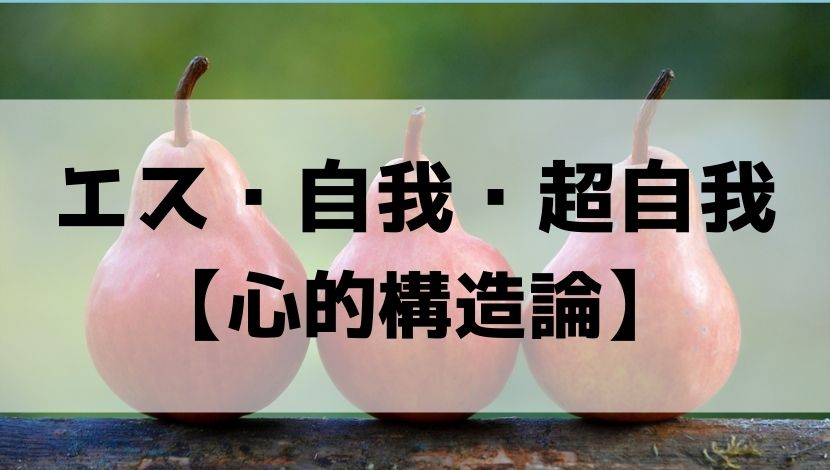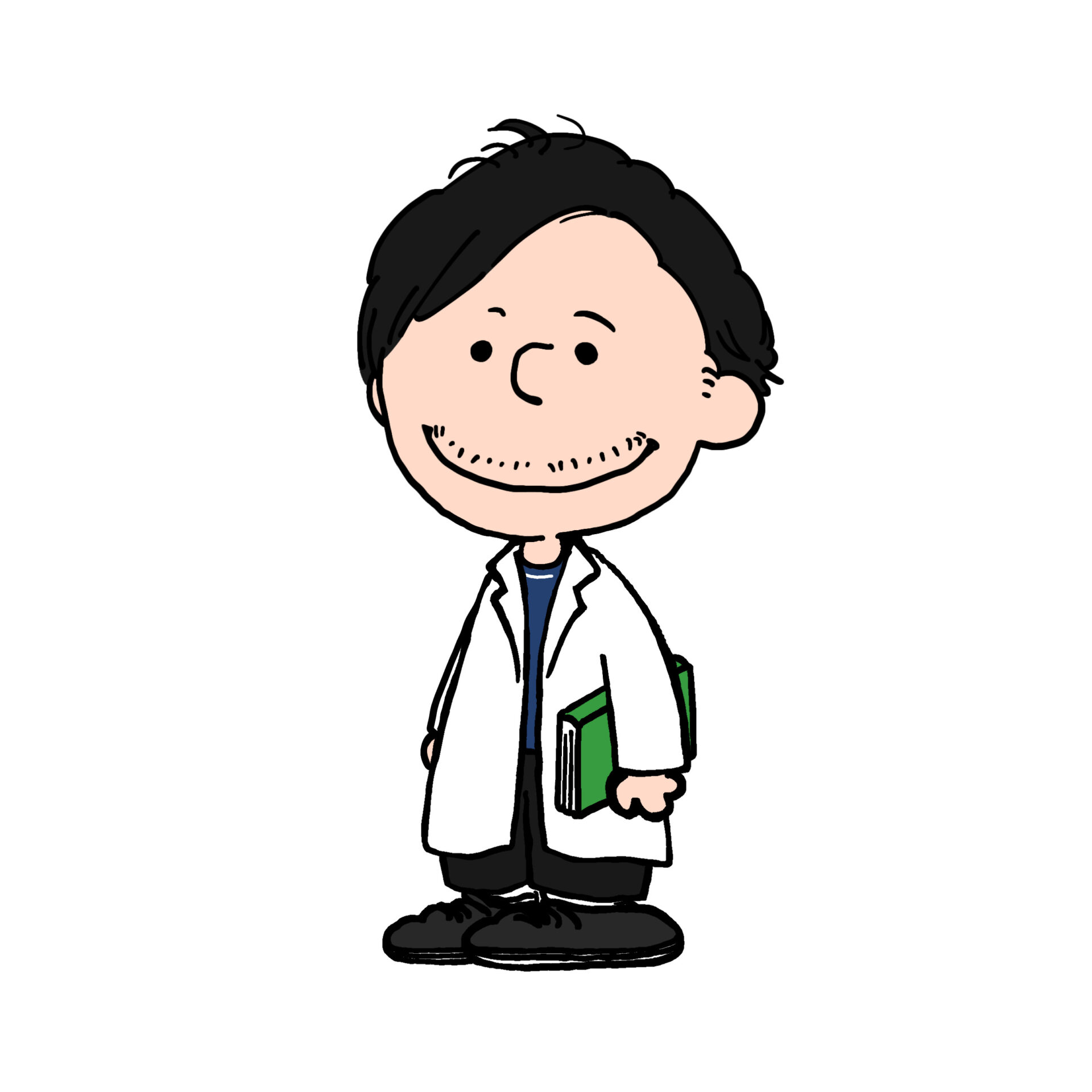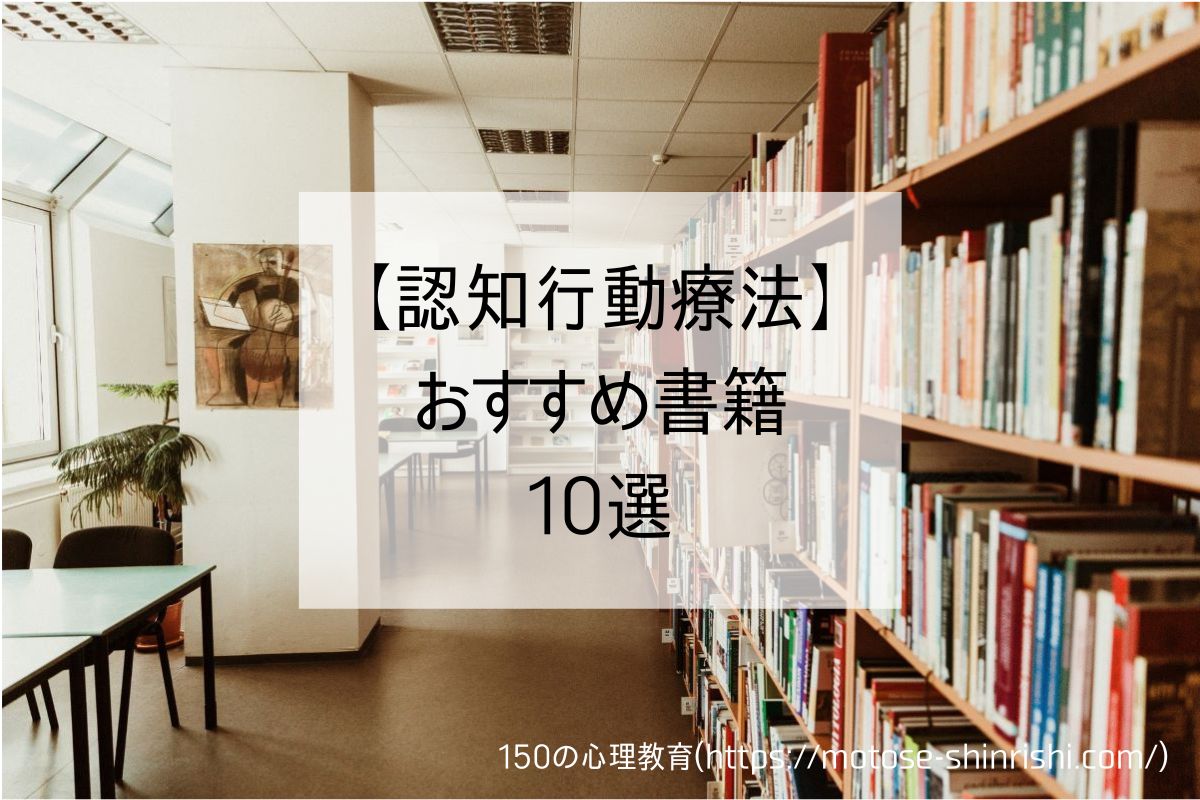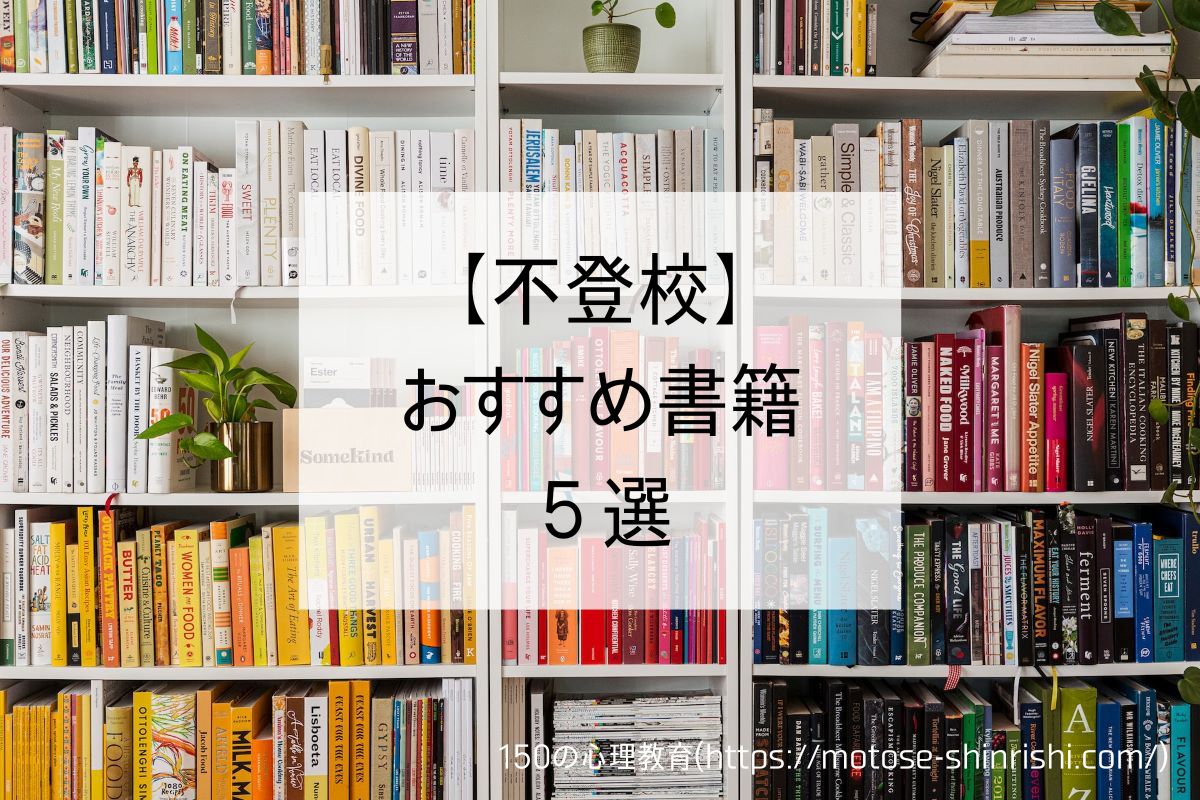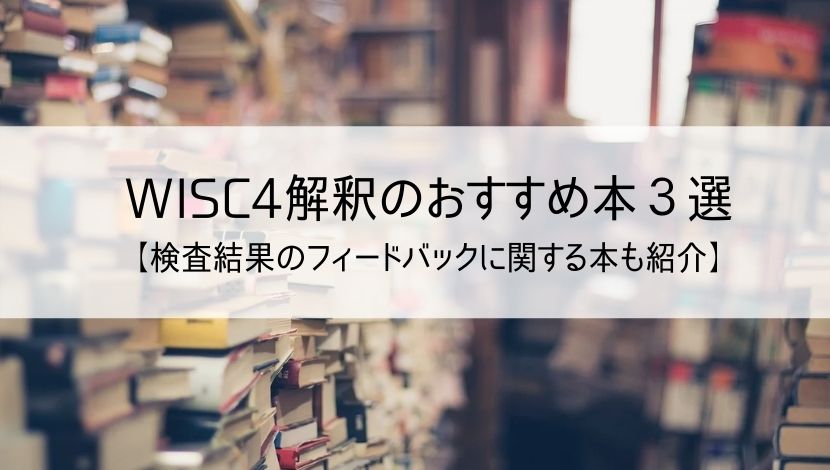こういった疑問にお答えします。
具体的には以下の感情心理学に関する学説を紹介します。
- 情動の末梢起源説(ジェームズ・ランゲ説)
- 情動の中枢起源説(キャノン・バード説)
- 情動の二要因説(シャクター・シンガー説)の3つ
皆さんは悲しいから泣くのか、泣くから悲しいのか、どちらだと思いますか?
私は悲しいから泣く、方がしっくりきます。泣くから悲しいというのは現実的な感覚としては実感しづらいのではないでしょうか。
では、心理学的にはどちらが正しいと考えられているのか紹介します。
はじめに:情動と気分って違うの?
心理学的な感情の理論に関しては3つほど有名なものがあります。
情動の末梢起源説、情動の中枢起源説、情動の2要因説の3つです。
ちなみにこの情動というのがいわゆる感情のことなのですが、この「情動」という言葉は厳密にいうと「情動」と「気分」という2つの言葉にわけることができるようです。
- 情動:喜び、怒りなどの強くて一時的な感情
- 気分:楽しい・イライラするなどの弱めだが持続的な感情
豆知識でした。では、理論を1つずつ見ていきましょう。
情動の末梢起源説(ジェームズ・ランゲ説)
これはジェームズさんとランゲさんが唱えた説なので、別名ジェームズ・ランゲ説といいます。
ちなみにジェームズさんはアメリカ心理学会の代表になったこともある超有名な人です。
名言もたくさんありまして、例えば
“人間は幸せだから歌うのではない。歌うから幸せになるのだ。”
とか
“心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。
習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。”
などがあります。
それはおいといて、この末梢起源説によれば、まず初めに生理的変化が先に生じ、その変化を脳が受信することで情動が発生すると考えられています。
この生理的変化が “泣く”とか“笑う”という身体的な変化のことです。
末梢というのは末梢神経系のことを指しています。これは中枢神経系(脳と脊髄)に対する言葉で、ようはさきっちょの部分のことです。脳より、さきっちょである身体の部分が先ということで、末梢起源説といいます。
一般的に考えられる「情動をもとに生理的変化が生じる」とは逆のケースであるため、批判も多いです。
その批判の中でも最も有力なのが次の情動の中枢起源説です。
情動の中枢起源説(キャノン・バード説)
キャノンさんとバードさんによる感情生起の仮説です。
この理論は、外部情報により脳の視床が活性化し、そこから身体反応と情動体験が同時に生じるという説です。
この考えでは、外部刺激の情報はまず脳の視床を通過し、2つに分岐します。
片方は大脳に到達し、そこで恐怖や怒りといった情動が作られ、もう片方は視床下部に到達し、そこで体の生理的変化を起こす命令が作られます。
視床は、末梢神経系に生理的変化を引き起こす命令を送りますが、末梢神経が変化する速度は比較的遅いため、情動の経験が先に起こることになります。
この説は要するに、大切なのは中枢(つまり脳)で、感情の知覚は生理的変化よりは先に生じるという理論で、末梢神経系が先であるというジェームズ・ランゲ説を批判しました。
情動の二要因説(シャクター・シンガー説)
最後は情動の2要因説です。
これは、情動の生起には生理的喚起と、その生理的喚起に対する認知的解釈の2要因が必要となるという説です。
シャクターとシンガーの実験によって示されたのでシャクター・シンガー説ともよばれています。
ジェームズ・ランゲ説の弱点は、同じ生理的変化でも抱く感情が異なることを説明できない点です(例えば面接の前で緊張するドキドキと恋愛でのドキドキは同じ心臓のドキドキなのに、抱く感情は違うことを説明できない)。
情動の二要因説は、ドキドキといった生理的喚起のあとに、自分がドキドキしているのは面接の前だから緊張しているせいだ、という認知的解釈が入ることで感情が生起するという仮説です。
これなら生理的変化が同じでも抱く感情が異なることを説明できます。
情動の二要因説は、情動の生起に関して身体反応を重視するという意味で、ジェームズ・ランゲ説を再評価するものであり、またつり橋効果やロミオとジュリエット効果など、帰属錯誤から生じる情動理論の基礎を築きました。
結論はどっち?
感情の理論を紹介しましたが、「泣くから悲しいのか、悲しいから泣くのか」どっちなのかについては、心理学的には決定的な結論は出ていません。
しかし、二要因説でも生理的変化を重視しているように、身体の変化というのはバカにできないのは確かなようです。
さいごに:感情心理学お勧め書籍
ベーシックな入門書は以下が良いと思います。私も持っています。
公認心理師対応の本もあります。
他にも心理学コラムの記事がありますのでよかったらご覧ください。